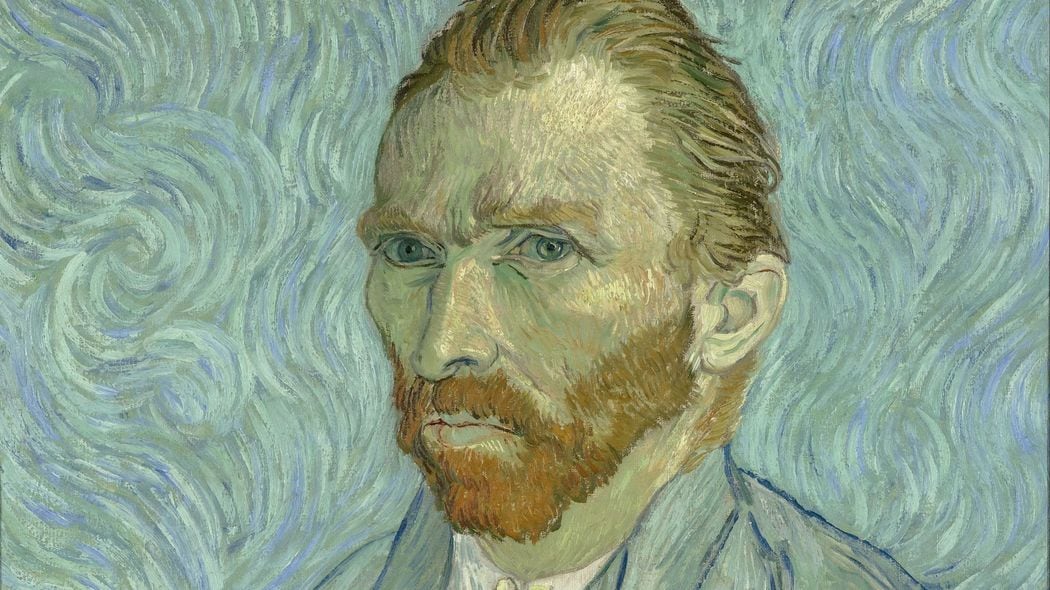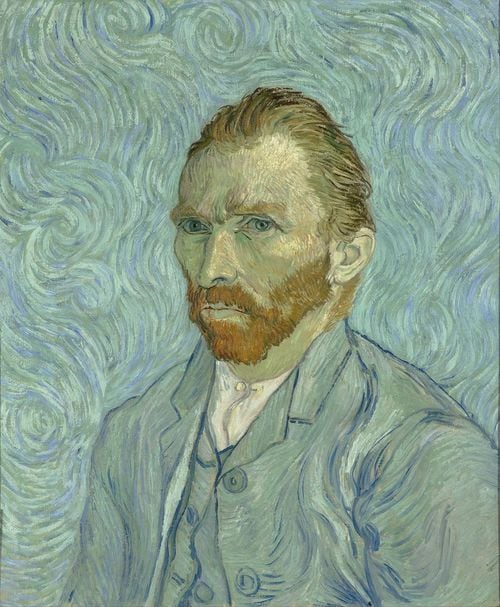※本稿は、西岡文彦『わかるゴッホ』(河出文庫)の一部を再編集したものです。
転落する兄と飛躍する弟
失恋と失業が、ゴッホを画家にしたといえる。
20歳で初めての失恋を経験する以前、ゴッホは当時、パリの一流の画廊・グーピル商会のきわめて優秀な職員として、将来を期待されていた。
失恋から立ち直れなかったおかげで職を失うことがなければ、ゴッホが牧師を志すことはなかったであろうし、牧師になる夢に、神に見放されるようなかたちで破れることがなければ、ゴッホは画家になっていなかったに違いない。
当時、オランダの行政と文化の中心であった大都市ハーグの支店に入った16歳のゴッホは、以降、20歳までは模範的な画商見習いとして勤務しており、実家の家計を助けるまでになっている。誠実勤勉な働きぶりは、同僚や顧客からの人望も篤く、両親の自慢の息子であった。
4年後、4歳下の弟テオドルス・ファン・ゴッホ通称テオが、兄と同じく16歳で同社に入って後は、先輩店員として激励と指導の手紙を送り続けている。
1878年のパリ万博の会場で日本館が熱狂的な人気を集めていた当時、ゴッホは25歳になっていた。失恋の痛手から画廊の職を失い、書店員や教師の道にも挫折、牧師を目指して始めた神学大学に進むための受験勉強も長くは続かず、オランダで伝道師となる夢も絶望視され始めた頃のことであった。
翌年、ゴッホのその夢は、無給の牧師見習いとして派遣されたベルギー南端の極貧の炭坑地帯ボリナージュで完全に断たれることになる。
対照的に、弟のテオの人生が一挙に開けたのがこのパリ万博でのことだった。
会場内のグーピル商会の展示場に立ち寄ったフランス大統領マクマオンを、オランダから来たこの若者が堂々たる態度で接客し、テオがグーピル商会に不可欠の逸材であることを証明してみせたからである。
ジャポニスムの誕生と歩調を揃えて始まったゴッホ兄弟の職業人としてのキャリアは、パリの日本ブームが頂点を迎えるこの時期には、兄と弟の評価を完全に逆転させてしまっていたのである。
ゴッホが、ベルギーの養成所で伝道師の適性を欠くと判断された頃のことである。
やがてゴッホは、ボリナージュで、貧困と苦役にあえぐ人々の姿を素描に描き始めることになる。
人々と苦難を分かち合い、祈るような思いで素描を描くゴッホにとっては、パリを熱狂させるジャポニスムは、まだ文字通り異国の事件でしかなかった。