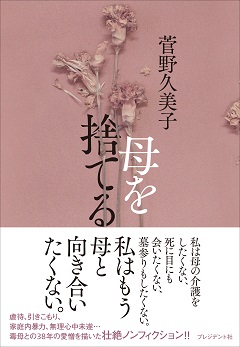ゼロ年代以降にあまり見られなくなった母娘の葛藤
【菅野】私は専業主婦だった母から肉体的、精神的、ネグレクトなど、ありとあらゆる虐待を受けて育ちました。それで、いつも思い出すのが、私が小学生から高校生までを過ごした90年代という時代なんです。私自身、母の教育虐待やいじめでひきこもりになったり、最も苦しかったのが90年代です。
1990年代はいまのように気軽にSNSなどで自ら発信をしたり、情報を得たりすることは簡単ではない時代でした。それでもインターネットがゆっくりとながら、一般家庭に普及しはじめた。
私自身、ひきこもりにありがちな昼夜逆転の生活を送りながらも、ネット上の掲示板で見つけた家族以外のつながりが救いになったんです。だからこそ今一度、90年代を振り返ってみたい。
そんな90年代の「母娘」を取り巻く状況は、どのようなものだったのでしょうか。
【斎藤】80年代初頭に当時20歳の青年が教育虐待の末、両親をバットで殺害するという「金属バット殺人事件」が起きました。その少し前の70年代後半に起きた「開成高校生殺人事件」は、それとは逆に親が子どもを殺した事件でしたが、こちらにも教育問題が絡んでいたと記憶しています。
90年代にそうした教育が絡む特異な事件があったかといえば、目立ったものはありません。ただ、そうした教育を取り巻く殺伐たるムードはその後も一貫して存在していたと思います。
90年代は母娘支配の最盛期
【斎藤】一つ言えるのは、今あげた事件は「母娘」ではありませんが、少なくとも「母娘」の葛藤は、ゼロ年代以降にはあまり見られなくなってきたということです。「友だち親子」や「一卵性母娘」という言葉が象徴するように、親は子どもを支配することなどほとんど考えず、子どもに嫌われたくないので「叱るのは学校の先生任せ」のようになっていきました。
【菅野】私自身、孤独、孤立問題について取材しているのですが、2000年代前半以降は母親に悩みを相談する若者も増えてきていると聞きます。「深刻な悩みは友だちに相談できないから、母親に相談する」というふうに変化しているようですね。
【斎藤】最近はアンケートなどで生徒に「尊敬する人は誰か」をたずねると、「両親」などと答える人がとても増えていると聞きます。われわれ世代では考えられません(笑)。これも、そうした傾向を裏付けているのではないでしょうか。
「支配」という観点からいうと、特にゼロ年代以降はいい変化があったといえます。おそらく菅野さんが経験した90年代は、母娘支配の真っ只中だったはずです。
【菅野】まさに真っ只中です。それを考えると、いちばん大変な時代だったんですね。母親の行き場のないマグマのようなエネルギーのようなものを日々感じていましたし、子どもながらそのパワーに押し潰されそうで、まさに「出口なし」でしたね。