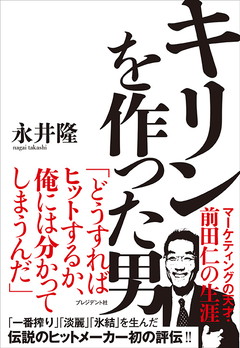缶チューハイの「氷結」が焼酎ベースでないワケ
「チューハイ」とは焼酎を炭酸水で割るから、その名がついた。ところが、「氷結」は缶チューハイでありながらベース酒に甲類焼酎ではなくウオッカを採用した。
その理由はとてもシンプルだった。キリングループには焼酎の製造免許をもつ工場がなかったのである。
その一方で、キリン・シーグラム御殿場蒸溜所は、ウイスキーとともにウオッカも生産していたのだ。
ウオッカベースのカクテルは、モスコミュールやソルティドッグ、バラライカ、スクリュードライバーなど数多い。甲類焼酎より「ウオッカを使ったほうが、癖がなく飲みやすい味わいになる」(鬼頭)との前例にとらわれない仮説を立て、私的なプロジェクトは試醸を繰り返していった。
缶チューハイは、84年に宝酒造が「タカラcanチュ-ハイ」、東洋醸造(現在はアサヒビールに譲渡)が「ハイリキ」を相次いで商品化したのが始まり。99年にはサントリーが「スーパーチューハイ」をヒットさせるが、いずれも中高年向けで、アルコール感が強く、飲み応えを追求していた。
鬼頭はこれらオヤジ向け缶チューハイを、「第1世代の味」と社内的に定義した。
それまでの缶チューハイに対しキリン・シーグラムの2人が狙ったのは、若者向け缶チューハイだった。特に、そもそもアルコール飲料とは縁の薄い20代から30代の女性を取り込もうと考えたのだ。
「男女雇用機会均等法(1986年施行)で大手企業に入社した女子総合職一期は、すでに30代半ばを迎えている。彼女たちが仕事を終え、一人暮らしのマンションに帰り、冷蔵庫を開けて飲める酒」「働く女性が新幹線のなかでも飲める、お洒落な缶チューハイ」……。
キリンの戦略転換で白羽の矢が
親会社のキリンビールのマーケティング部長となっていた前田は、鬼頭と和田を自由に泳がせていた。
そんな前田が、「一度サンプルをもってきてくれないか。できれば大至急」と2人に要請したのは2000年春。
実はこの頃、キリンは「総合酒類化」を模索していて、正式には00年9月に打ち出す。総合酒類化はビールや発泡酒だけではなく、幅広く酒類を展開していこうとする戦略の転換を意味した。
消費者の嗜好が多様化し、少子高齢化と人口減少が進む日本で、ビール系飲料だけでは先細りになるのは、目に見えていた。すでに、ビール単品で高いシェアを獲得すれば収益を確保できる時代ではなくなっていたのだ。多様化するユーザーニーズに応えなければならなかった。
マーケ部長の前田は、総合酒類化の第一弾商品として、2人が私的に取り組んでいたウオッカベースの缶チューハイに白羽の矢を立てたのだ。