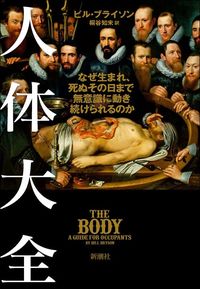記憶は永久の記録ではなく、揺れ動くもの
記憶の保存は特異なプロセスで、奇妙なほど支離滅裂だ。
脳はそれぞれの記憶を部品ごと――名前、顔、場所、情況、手触りはどうだったか、生きていたか死んでいたかまで――に分け、その部品をさまざまな場所に送り、全体がふたたび必要になると、呼び戻して組み立てる。
ふと浮かんだひとつの考えや追想が、脳全体に散らばった100万個以上のニューロンを発火させる。しかも、こういう記憶の断片が時とともに脳内を動き回り、なぜだかはまったくわからないが、大脳皮質のひとつの場所から別の場所へ移動する。記憶の細部がごちゃまぜになってしまうのも無理はない。
要するに、記憶はファイリング・キャビネットに収めた書類のように固定された永久の記録ではない。もっとずっと漠然としていて、移ろいやすいものなのだ。エリザベス・ロフタスは、2013年のインタビューでこう語った。「少しウィキペディアのページに似ています。あなたはそこに入っていって書き換えることができるし、ほかの人も同じように書き換えられます」。
子どものころの記憶はどこに消えた?
以前は、あらゆる経験は記憶として脳のどこかに保存されているが、そのほとんどは、即時想起の力が及ばないところへしまい込まれてしまうと考えられていた。
その考えはおもに、神経外科医ワイルダー・ペンフィールドが1930年代から1950年代にカナダで行なった一連の実験から導き出された。
モントリオール神経学研究所で手術を行なっているとき、ペンフィールドは、探針で患者の脳に触れると、しばしば強烈な感覚が呼び起こされることを発見した。
子どものころに嗅いだ懐かしい匂い、すばらしい幸福感、ときにはごく幼いころの忘れていた場面を思い出すこともあった。こういう事実から、脳はどんなに些細なことであっても、意識を伴う人生のあらゆる出来事を記録し保存しているという結論に行き着いた。しかし現在では、ほとんどの場合、刺激が記憶の感覚を与えているだけで、患者が経験したのは、思い出した出来事というより、幻覚に近いものだったと考えられている。
けれども、わたしたちが簡単に思い出せるものよりはるかに多くの記憶を保持しているのは、確かな事実だ。
幼いころに住んでいた近隣についてはあまり思い出せないかもしれないが、そこに戻って歩き回れば、何年ものあいだ頭に浮かびもしなかった取るに足りない細部まで、ほぼ確実に思い出すだろう。
じゅうぶんな時間と刺激があれば、おそらく誰もが、自分の中にどれほど多くのものがしまい込まれているかを知って驚くだろう。