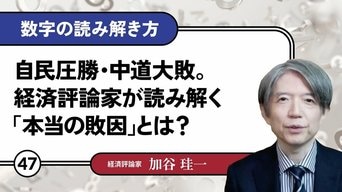「ばけばけ」(NHK)ではラフカディオ・ハーンをモデルとするヘブン(トミー・バストウ)がイライザ(シャーロット・ケイト・フォックス)と再会。作家の工藤美代子さんは「ハーンはアメリカ人女性を痛烈に批判したが、心を許した相手がいた」という――。
※本稿は、工藤美代子『小泉八雲 漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』(毎日文庫)の一部を再編集したものです。
日本の怪談が好きすぎたハーン
ハーンの『怪談』は、あまりにも有名ですが、その創作過程について、妻のセツが「思い出の記」の中で興味深い記述をしています。
「怪談は大層好きでありまして、『怪談の書物は私の宝です』といっていました。私は古本屋をそれからそれへと大分探しました。淋しそうな夜、ランプの心(芯)を下げて怪談をいたしました。ヘルンは私に物を聞くにも、その時には殊に声を低くして息を殺して恐ろしそうにして、私の話を聞いているのです。その聞いている風がまた如何にも恐ろしくてならぬ様子ですから、自然と私の話にも力がこもるのです。その頃は私の家は化物屋敷のようでした。私は折々、恐ろしい夢を見てうなされ始めました。」
これは、少し穿った見方かもしれませんが、ハーンにしてみれば、妻のセツが夢にうなされるくらい怪談の世界に深入りしてくれなければ困ったのではないでしょうか。理性的な女性で怪談は迷信と片付けるか、そこまではゆかなくとも、創作に必要な素材と割り切るようだったら、物語そのものにあれだけの凄みとか迫力が出なかったと思うのです。
しかも、さらに見逃してはならないのは、セツ自らが古本屋を歩き、作品に使えそうな本を捜しだし、それを買い求めて読んで、自分の体内でいったん消化してから、夫に話して聞かせたことでした。これは大変なインテリジェンスを必要とする行為です。たとえばアメリカの大学などの英作文のクラスでは、必ず物語の要約、サマリーが課題として出される例などを見ても、それが如何に難しい知的作業であるかがわかると思います。
ハーン「日本女性は何という優しさ」
生涯で初めて自分の私生活のみならず仕事の面でも良き伴侶となるセツに巡り会ったハーンは、日本女性への賛辞をチェンバレンに宛てて次のように書いています。
「しかし、日本女性は何という優しさでしょう! ――善性に対する日本民族の持てるあらゆる可能性は、女性に凝集しているように思われます。このことは、西洋の原則のいくつかに対する人の信仰を揺るがすものです。もしこの優しさが抑圧と圧制の結果であるとするならば、抑圧と圧制も全面的に悪いとは言えません。これに反してアメリカ女性は、自分が偶像崇拝の対象となりながら、その性格をどんなにダイヤモンドよろしく硬直させてしまうことでしょう。」