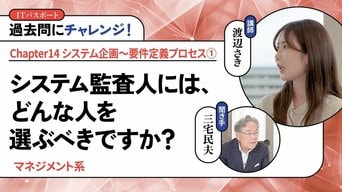※本稿は、工藤美代子『小泉八雲 漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』(毎日文庫)の一部を再編集したものです。
10年ぶりに彼女と文通を再開する
ラフカディオ・ハーンとエリザベス・ビスランド。10年ぶりにふたたび開始された2人の文通で、ハーンは彼女にアメリカでの仕事の斡旋を依頼しました。これに対してビスランドは誠実に答えるのですが、ハーンの筆致はまたたくまに卑屈になってしまいます。
「実際、私はあなたをわずらわせる権利などありませんし、また、そんなことを思ってもいません。ただ妖精の女王に祈っているというだけのことです。親切にも聞いてやろうとなさるのでないかぎり、あなたが耳を傾けてくださる必要はありません。」
「あなたは、旧い知人を小さな白髪の不快な“老人”と思ってみるべきなのです。」
1902年7月2日付けの手紙ですが、ハーンの彼女への屈折した感情が言葉の背後に浮び上がって見えます。
そして、ここで一つ思い出さなければならないのは、ハーンが基本的には白人の女性にあまり良い感情を抱いていなかったということです。それは友人のチェンバレンへの手紙の記述を見てもわかると思います。ところが、ビスランドにだけは、心を開いて何でも語っています。それはなぜだったのでしょう。
ハーンと彼女が共有していた本質
もしも大胆な仮説が許されるなら、私は彼女とハーンの間には、ある共通項があったと思うのです。それが2人を結びつけたのです。では、その共通項は何かというと、漂泊の魂なのです。

19世紀末のアメリカは、知と富を手に入れ、世界中のあらゆる地点に人間が散ってゆきました。それは何も男性にだけ起きた現象ではなかったのです。女性もまた、空間へのコントロールを得ようとしていました。
エリザベス・ビスランドは南部の大農場主の娘に生まれ、文筆で身を立てるべく10代の終わりにニューオーリンズに来ました。ハーンと出会ったのはそこの新聞社でした。彼女が21歳の時のことですが、どうしたわけかハーンは彼女が16歳くらいだったと記憶しています。
ハーンがニューオーリンズを去るより早く、ビスランドはニューヨークへ行ってしまいます。持ち前の才気と美貌で、たちまち『コスモポリタン』など一流の雑誌に原稿を書くようになりました。そしてハーンが日本へ発つより先に彼女は世界一周の旅に出ています。これは、当時アメリカでトップクラスの女流ジャーナリストだったネリー・ブライと、どちらが早く世界一周ができるかを競う出版社の企画だったのです。結局4日間の差でビスランドは負けます。しかし、世界一周の途中でハーンより以前に横浜の土を踏んでいるのは興味深い事実です。