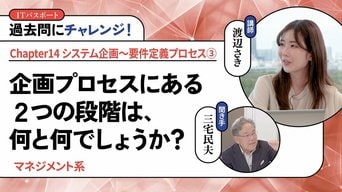※本稿は、木村映里『医療の外れで 看護師のわたしが考えたマイノリティと差別のこと』(晶文社)の一部を再編集したものです。
※病院のエピソードは患者の個人情報の守秘義務上、疾患、背景、シチュエーションなど、個人特定に繋がらない段階まで脚色、改変しています。
ベッドの柵に顔を打ち付けられる
何年か前に、患者さんに髪を掴まれてベッド柵に顔を打ち付けられた時のことを思い出す度、ぶつけたのが頬で良かったなあ、眼だったら網膜剥離とか眼窩骨折とか下手すると失明だったなあ、コンタクトレンズが割れて目に刺さったら危なかった。
やば。なんて、のん気に考えてしまうのですが、それが暴力を受けた恐怖の自分なりのやり過ごし方だと気付いたのはつい最近のことでした。
80代男性の山本さん(仮名)は路上で転倒して動けなくなり、救急搬送され入院となりました。肋骨骨折の診断を受けた翌日、山本さんは突然「俺は帰る」と、帰宅を希望しました。真冬で、独居生活であったことから、すぐに家に帰ったところでまともに生活が送れないどころか、下手すると家で動けなくなり、命すら脅かされることは誰の目にも明らかでした。
その日の受け持ち看護師だった私は、ベッドに座って「帰らせろ!」と大声を出す、少しだけ耳の遠い山本さんに、「そうですよね、辛いですよね」「気持ちはわかりますが、今は病院で痛みを取りましょう」と、腰をかがめ、目線を同じ高さに合わせて語りかけました。
「お前何様なんだ! 帰るんだよ馬鹿野郎! 患者の言うことが聞けないのか!」と怒鳴り続け、脇腹の痛みに顔を歪ませながら立ち上がろうとする彼に「帰りたいですよね」と同意した直後、山本さんの手が私の顔前を横切りました。
頭皮に痛みが走り、髪を掴まれたと認識しましたが、抵抗する間もなく目の前の景色がぐらりと揺れ、ゴンッ、という鈍い音と共に、私は鉄製のベッド柵に顔を打ち付けられていました。「やかましいんだよ! 馬鹿女が!」という山本さんの声が聞こえ、続けて二度、左頬に痛みが襲い掛かり、私は悲鳴を上げることすらできませんでした。