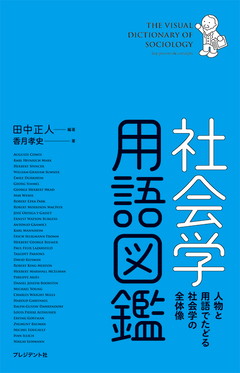セクハラ問題化のメルクマール「京大矢野事件」
日本でセクハラ問題化のメルクマールになったのが、1993年の京大矢野事件です。
京都大学東南アジア研究センターの所長だった矢野暢氏の研究室で、ある年に複数の若い女性秘書がたてつづけに辞めてしまった。矢野氏に命じられて、先輩秘書が辞めた秘書たちにヒアリングに行くと、矢野氏による数々のセクハラが明らかになりました。先輩秘書もまた、矢野氏から同じ目に遭っていたことがわかり、先輩秘書はこれ以上の被害者が出ないように、思い切って京都市弁護士会に対して人権救済の申し立てに踏み切りました。つまり、この女性はクレームメイキングをしたんです。
申し立てを受けて、京都大学の女性教官懇話会代表の小野和子さんが、矢野氏を告発する記事をメディアに寄せます。これに対して矢野氏は名誉毀損で逆に訴訟を起こしますが、裁判の過程で矢野氏が行なった行為が却って事実認定され、矢野氏の敗訴になりました。
ただ、このとき京大の男性教員の一部では、「たかがセクハラごとき小事で、有為の人材を失っていいのか」という声が上がり、告発をやめさせるような動きさえありました。
また、朝日新聞の東京本社版では矢野事件についての特集を3日間にわたって組みましたが、大阪版の紙面にはついに掲載されませんでした。矢野氏が関西の著名な研究者で影響力が大きいから忖度が働いたからだろうと推測していましたが、あとから関係者に聞いたところでは、大阪本社のデスクがセクハラには報道価値がないと判断したそうです。それほど、セクハラは「小事」だと考えられていたんです。
啓蒙によって「小事」を「大事」に
「セクハラ」が流行語大賞に選ばれたのは1989年ですが、当時の男性主導のメディアではセクハラは「アホな女がつまらないことを言い立てている」といった揶揄的な調子で語られていました。「おっぱいを揉んだりお尻を触ったりするのは職場の潤滑油」「そんなこともできないなんて、職場がギスギスする」という声が出ていたくらいです。
そんな認識を、裁判の過程で一つ一つ変えていったんです。たとえば、横浜セクハラ裁判では、被害者がセクハラを受けた後、弁当を食べたことが問題になりました。裁判官も検事もおっさんの感覚丸出しでしたから、「被害を受けたといっても、そのあと平然と冷静な行動をとっていたのだから大したことではないのだろう」と解釈して、被害者の供述には信用がおけないなどと判断を下しました。
ですが、トラウマ的な被害を受けた人は、できるだけ日常的なルーティンを繰り返すことで、被害による傷をやり過ごそうとする心理的な規制が働きます。
これに対して弁護士やカウンセラーたちが意見書を書き、性犯罪被害者のPTSDについての研究成果などを用いながら、裁判官を啓蒙していきました。そうして勝訴を一つ一つ積み上げながら、認識を変えていった。ファクトはそのような積み重ねによって作られるんです。