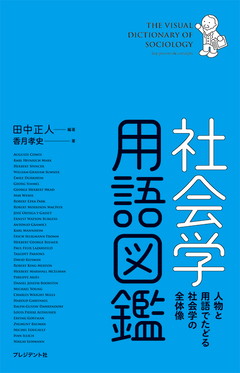カテゴリーがなければ「事実」は生まれない
社会学は基本的に「経験科学」です。つまり、人と人との相互の間に起こる、言及可能な現象を扱うのが社会学です。
でも、言及可能な現象を扱うといっても、カテゴリー化されていない現象はそもそも認識すらできません。たとえば「ドメスティック・バイオレンス(DV)」や「セクシュアル・ハラスメント(SH)」という概念は、かつては日本語にはありませんでした。いずれも海外から日本に導入された言葉ですから、今でもカタカナ言葉のままなんです。そうやって、カテゴリーを作ることで初めて、ファクトを切り出すことができるようになりました。
日本では1989年に初のセクハラ調査、1992年に初のDV調査が実施されましたが、そのときに「あなたはDVやセクハラを受けたことがありますか?」と訊いても、誰も答えられない。カテゴリー化されていなければ、何がDVやセクハラなのかすらわかりませんからね。
けれど、「あなたはこういう経験をしたことがありますか?」と具体的に訊くと、DVやセクハラの存在が明らかになります。たとえば、1992年に「夫(恋人)からの暴力調査研究会」が初めて実施したDV調査では、回答者のうち59%の女性が、跡が残るほどの肉体的暴力を夫から受けたことがあると答えています。そうやって、DVの存在というエビデンスを得ることができたのです。こういう調査研究のあり方を、問題解決を志向するアクション・リサーチと呼びます。
言語で切り出すことによって「カテゴリー化」する
ただしこの調査はスノウボール・サンプリングと言われるもので、データに客観性がありません。この59%という数字が世界に出回ったおかげで、日本は野蛮な社会だという国際的なイメージが定着するのを怖れた日本政府が、2005年になって史上初の「科学的調査(ランダム・サンプリングによる)」を実施したところ、身体的暴力の経験率が27%、カナダ25%とアメリカ28%の中間値で、先進国標準ということがわかりました(笑)。民間の調査があったからこそ、それに押されて、公的な機関が調査に踏み切ったのです。
つまり、エビデンスは誰が見てもその存在がわかるものとして最初からあるわけではありません。何か違和感や問題を感じた人がクレームを申し立てて、言語によって切り出すことによってカテゴリー化する。それによって初めて問題として、成立します。だから、フェミニストはみんな「許せない」「ガマンできない」「こんなバカなことがあっていいわけがない」と問題を訴えるクレーマーでした。セクハラだって、「もやもやする」という体験に、セクハラという新しい概念が登場して、カテゴリー化を可能にしたんです。