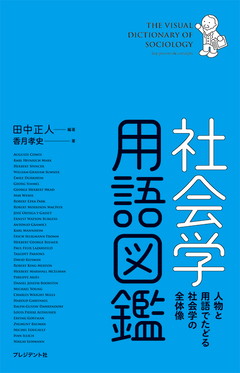今年4月、東京大学の入学式で社会学者の上野千鶴子氏が述べた祝辞は話題を集めた。そこで上野氏は「女性学」という学問を作り、研究者として社会の不公正と闘ってきたと述べた。なぜ上野氏は学者という「説明屋」に甘んじず、運動家として社会変革を謳ってきたのか。本人に聞いた――。(後編、全2回)
自己責任論が人々の連帯を阻む
東京大学の入学式の祝辞では、18才の子どもにもわかるやさしい言葉でしゃべるようにつとめましたが、学術用語をひとつだけ使いました。「アスピレーションのクーリングダウン(意欲の冷却効果)」です。東大の女子学生比率は2割の壁を超えません。女性たちは、「どうせ女の子だし」「しょせん女の子だから」と水をかけられ足を引っ張られることでくじかれてしまい、本当にやりたいことを選択できなくなるのです。
もし新入生たちが「がんばれば公正に報われる」と思えているのだとしたら、そう思えること自体が、努力の成果ではなく環境のおかげだということを忘れないでと伝えました。
この祝辞に対して、「東大の女子の割合が2割以下なのは女の子たちが自己選択した結果、受験者が増えないだけなのだから問題ない」といった反応がありました。これは「自己決定・自己責任」の論理です。でも、あの短い祝辞の中に、それに対する反論はちゃんと書いてあるんですけどね。
この数十年で、ネオリベラリズム的な「自己決定・自己責任」のメンタリティが浸透したことを強く感じます。だから、その人の不遇や困難は自己責任であるということになってしまう。自己責任がこれだけ定着して強く内面化されると、困難にある人たち同士で連帯できなくなってしまうんですよ。