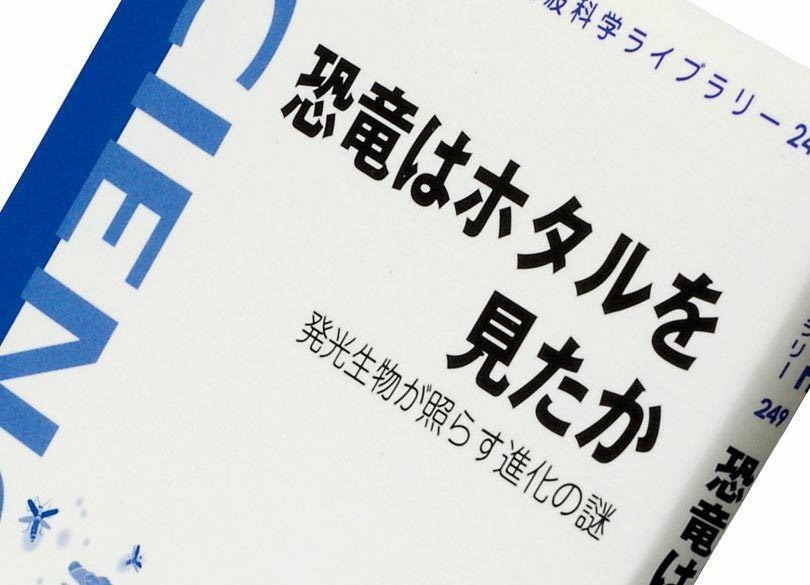夜になれば人は電灯をつけるが、ホタルなど自分で光る生物もある。あるとき一群の生物が発光する能力を手に入れ、光るものと光らないものとの間で、食うか食われるかの「進化レース」が始まった。
本書は発光を専門とする生物学者が、進化の道筋を巻き戻しながら光る生物の戦略を繙いてゆく。そもそも発光するのは他者を威嚇し自分が食べられないようにするためだ。
海には発光生物があふれているが、光ればすぐに見つかって食べられそうに思う。ところが逆で、海中で光るお陰で自分の下方にいる捕食者から見えないのだ。もし光らなければ、上から差し込む太陽の光で自身の影が映り、エサであることを示すことになる。
雌雄が異性を誘うため光を出す生物もいるが、人は今後どんなに進化しても発光しないそうだ。というのは、威嚇や伝達手段として、発光は効果的ではないからだ。仕方がないので我々人類は内面を磨いて輝くとしよう。
さて、タイトル「恐竜はホタルを見たか」への答えはイエスである。ティラノサウルスをはじめ恐竜たちはホタルの光を見ていたという。そしてこの問題は、恐竜に隠れて暮らしていた我々の祖先、すなわち原初哺乳類の食に関わる。
「ホタルが地上に出現した白亜紀の地上では、夜行性の原初哺乳類が虫を漁り歩いていた。このときホタルの幼虫は、自分がマズいことをアピールする方法として緑色に光る能力を進化させ、生き残ったに違いない」(68ページ)。
この仮説が本当かどうかの実験も行った。「私の知り合いが、試しにトガリネズミにゲンジボタルを一匹与えてみたところ、食べた直後から何度も嘔吐して、それから二度とホタルを食べようとはしなかったそうである。よほどマズかったようだ」(同ページ)。
つまり、「生物の味覚は進化の産物であり、なにが旨くて何がマズく感じるのかは、その生きものが歩んできた進化の道筋による。そして、苦みとは、基本的に食べられないものを忌避するための感覚である」(68~69ページ)。なるほど、食の感覚が太古から引き継いだ大事な能力であることがよくわかる。
こうした面白い話題を繰り出す著者が、本書をいかに書き上げたかも興味深い。「書きはじめると自分でも驚くほど筆は早かった。(中略)しかし、うろ覚えの情報を頼りに一気に書き上げたので、その後のファクトチェック(書いたことが正しいのかを原著論文に当たって確認する作業)は大変だった」(117ページ)。
そうなのだ。この地道な作業を行って初めて信頼できる科学書が誕生する。評者の専門とする地球科学でも、面白おかしく書くだけではダメで、科学的な事実と照合する膨大な時間を費やす必要がある。ここに専門家と素人の書き手との差が生まれる。