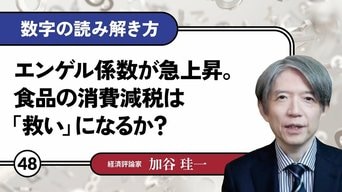「働きアリの2割は働かない」を、2年かけて実証
アリのコロニーにはほとんど「働かないアリ」が2割ほど存在する。そして「働かないアリ」が存在しないと、コロニーは長続きできない――。進化生物学者で北海道大学大学院准教授の長谷川英祐氏が率いる研究グループは、長期にわたるアリの行動観察やコンピュータシミュレーションを通じて、こんな意外な事実を発見した。一見、短期的には非効率に見える「働かないアリ」の存在が、組織の長期存続に大きな貢献をしている。近年、日本企業では短期的な効率重視に偏ったマネジメントが目立つが、虫の世界の「勝ち組」は、どうやら短期的効率一辺倒ではないようだ。

長谷川氏が8年ほど前から手がけたのが「働きアリの2割は働いていないと言われているが、それは本当なのか」というテーマだった。「ほとんど働かないアリがいることはわかっていた。またそれが2割程度だということがまことしやかに言われていたが、実際に調べた人は誰もいませんでした」。当時長谷川氏の研究室に所属した大学院生がアリの研究を希望したこともあり、このテーマを手がけることにした。
「ほとんど働かないアリが2割いる」と、結論を言ってしまえば簡単だが、このことを科学的に証明するには、実に2年の歳月を要した。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント