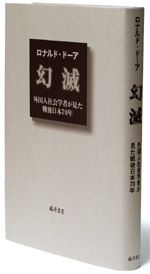
今年で90歳になる英国人社会学者ロナルド・ドーアの回想記。
ドーア教授は教育問題、労働問題が専門だが、戦後の日本研究の草分けでもある。戦後の「日本的経営」を高く評価しており、それがグローバリズムによって崩壊しつつあることを喝破した『働くということ』(中公新書)は10年前の刊行ながら、今でも読むに値する名著だ。その後も活発に著作を発表している。
回想記である本書『幻滅』には、当然ながらドーア教授の知的遍歴や交友が描かれている。同時に、本書は戦後日本社会の変容の年代記ともなっている。長年の労働党支持者のドーア教授は、当然ながら社会党が強く、保革伯仲の感のあった1980年頃までの日本を好ましく見ている。それは同時に日本経済が高度成長を遂げている時代でもあり、ドーア教授から見ても日本の知識人が輝いていた時代だった。丸山眞男、市井三郎、鶴見俊輔など、懐かしい名前が続々登場する。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント






