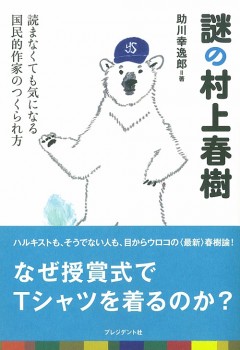――『半沢直樹』というよりは『ハゲタカ』っぽいですね。いつぐらいからこういう路線を意識していたんでしょう。
【助川】多分、『ねじまき鳥クロニクル』のあたりから、着々と海外移籍計画を進めてたんでしょうね。私の周りでも村上春樹は『ねじまき鳥クロニクル』で変わったという人は多いですよ。それまでのいわゆる、著者とほぼ同年齢の「僕」が「やれやれ」と言っている話が急に『ねじまき鳥クロニクル』でノモンハン事件のことを書いたり、『アンダーグラウンド』でサリン事件の被害者を直接取材したりして、いったい何をおっぱじめるんだという感じでしたね。あのあたりが転機だったのではないでしょうか。
ただ、最初から村上春樹は半沢直樹のように「あくまでも組織の中で戦う」人ではなく、そこに収まりきらない人だったわけで、私も含め、『ねじまき鳥クロニクル』で驚いていた人たちはそれが見えてなかったということですね。
――でも、半沢をこんなに好きな日本人が、いま1番好きな作家って村上春樹ですよね?
【助川】これには理由があって、まず、春樹を半沢だとまだ思ってる人がいる。伝統的なその春樹と同世代の、全共闘が終わっちゃって「やれやれ、もうこれ以上革命で頑張ってもしょうがないから、ちょっと後ろめたいけど社会人になってやるか」と、なったはいいけど、「でも俺、別に本気で会社人間やってないもんね」とか言って、会社に距離を置いているふりをしながら、実はもうどっぷり会社人間になっちゃってる人間のメンタリティと、春樹の「僕」のあり方がシンクロしているんですよ。
――ヨサクさんたちですか?
【助川】そう、ウンザリしながらも「仕方ないんだよね。やれやれ」といって組織から抜け出そうとしないヨサクさんたちは、学生運動にも消費社会にもシニカルなまなざしを向けていた「ように見える」村上春樹に自分を投影しているわけです。当然、ヨサクさんたちが好きなのは初期の作品です。