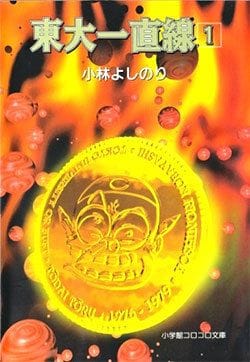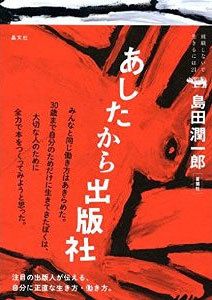昭和54年の文庫フェア
春の晴れた日に、空港でレンタカーを借り、断られた本屋さんを西から順に訪ねた。もちろん、この県にもチェーン店はたくさんあるのである。ただ、『本屋図鑑』という書籍の全体のバランスを考えると、この県では、チェーン店ではなく、地元にとけ込んだ、町の普通の本屋さんを取り上げたかった。
ぼくははじめに県庁所在地に行き、この県を代表するだろうチェーン店を2軒見た。ともに300坪以上の店で、平日の午前とはいえ、店内は常連のお客さんたちでにぎわっていた。専門書も充実しており、この県が決して本が売れないという土地柄ではないことが、なんとなく予測できた。
駐車場近くのコンビニでパンを買い、車のなかで食べながら、すぐに移動した。まずは車で30分ほどの距離にある隣の市から。
この10年で、日本のロードサイドの風景は、ほとんど同じになった。ぼくは車を運転しながら、見慣れた家電量販店や牛丼屋などの看板をながめた。同じ県道には、全国にチェーンを展開する某書店が、広い駐車場をかまえて営業していた。ぼくが行きたかったのは、ここから300メートルほど裏に入った、小学校の近くにあるA書店だった。
A書店は、坂の途中にある、20坪ほどの本屋さんであった。まわりは住宅地で、はす向かいに、パンやジュースなどを売る、むかしながらの食料品店があった。
店内に足を踏み入れ、すぐに、店主が電話で言っていたことが嘘でないとわかった。とにかく、本が少なかった。それなりに揃っているのはコミックだけだった。雑誌はそれぞれ1冊ずつ面陳(表紙が見えるように棚に陳列すること)され、夏目漱石や司馬遼太郎の文庫本でさえも、1冊ずつ間隔をおいて面陳されていた。単行本はというと、そのほとんどが日焼けし、返本できなくなったものばかりが店の片隅に並んでいた。店の3分の1は、なにもなかった。ただ、空っぽの本棚と、観葉植物だけが置いてあった。ぼくは挨拶すらできなかった。逃げるように、店を出た。
同じ市にある、もうひとつの書店は、A書店ほどではないにせよ、やはり本が少なかった。ここは15坪ほどの店で、単行本だけでなく文庫本もほとんど置いていなかった。残っていた文庫本はすべて日焼けしていた。A書店と違うのは、女性実用書が、少し活気があるように見えたことだけだった。
この日は、県庁所在地にある大型店と合わせると、計11軒の本屋さんをまわった。そして、絶望に近いような気持ちを味わった。
ぼくが訪ねた、チェーン店以外の店(計7軒)は、程度の差こそあれ、すべて、棚が埋まっていなかった。お客さんもほとんどいなかった。けれど、それとは対照的に、ロードサイドにあるチェーン店や、ショッピングセンターに入っている店には、少なくないお客さんたちがいた。違いは、無料の大きな駐車場があるか、ないか、それだけのように思えた。
ある書店主は、昭和40年の後半には、モータリゼーションの兆しがあった、と言った。そのころから人々は車で郊外へ出はじめた。商店街のにぎわいは、少しずつ失われていった。
この日訪ねた商店街の本屋さんには、昭和54年の文庫フェアが、そのまま綺麗に残っていた。「講談社文庫 推理・SFフェア」という赤い帯がついた文庫が、ずらっと文庫棚に並んでいた。コミック売り場に行くと、同じく、昭和50年代前半に人気をはくした『東大一直線』が、書棚を埋めていた。
完全に、時が止まっていた。
人がいなくなった町の本屋さんに来ているかのようだった。
もちろん、帳場には人がいた。
テレビを見ていたその老婆に、ぼくは昭和54年の文庫を差し出した。取材依頼の電話をした者です、とは口がさけても言えなかった。
「260円です」と老婆は言った。
「消費税は?」と聞くと、「まけときますよ」と言った。
●次回予告
大きさや、並んでいる本や、どの町にあるかといったことに関わらず、島田さんは自分が「いいなあ」と思う本屋に共通項があることに気づく。そういう本屋で聞こえてくる声がある。次回、連載最終回《本屋のこれから》、9月1日更新予定。