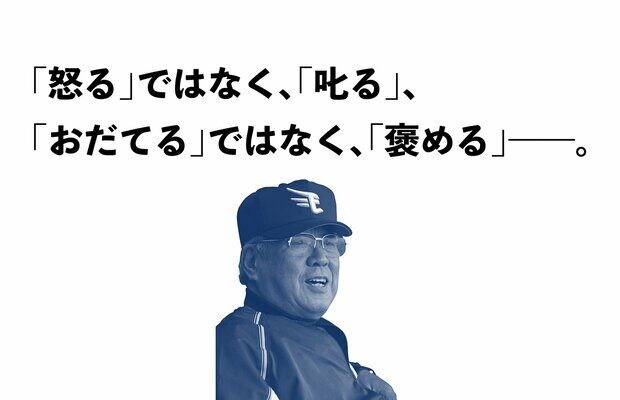人材育成において、どのように部下と接すればいいのか。かつて、「野村再生工場」と呼ばれ、他球団でくすぶっていた選手たちの才能を開花させた野村克也さんは、「怒る」と「叱る」の違いを明確に理解したうえで、「怒る」ではなく、「叱る」ことを心がけていたといいます。両者の違いはどこにあるのか? そして、その効用とは何か? ノンフィクションライターの長谷川晶一さんが分析します。
「褒めて育てる」とは対極的な野村の考え
近年では「褒めて育てる」という指導法が一般的であるが、野村克也は違った。一貫して、「わたしはそうは思わない」といい、「叱ってこそ育つ」という正反対の立場を貫いていた。その理由は、「褒められるばかりで、叱られることなく育った人間は、社会に出ても褒められることが普通のことだと思って、ちょっとした苦難に遭遇するだけで挫折し、落ち込んでしまうから」というものだった。
近年、自分のことを最優先して、他者に対する思いやりや気遣いができない自己中心的な人間が多くなっているのも、「褒める教育が関係しているのかもしれない」と述べている。野村自身、「褒めるのは照れくさくて苦手だ」と語っているが、決して選手たちを褒めなかったわけではない。「褒める」効用だってもちろん理解していた。それでも、選手たちの指導方針の根本にあったのは、「叱る」だった。
選手たちは、叱られることで反発する。野村は、その気持ちを重視していた。その反発こそ、成長に不可欠なものだと考えていたからだ。監督から叱られることで、選手は何かを感じ、「なぜ叱られたのか?」「何が悪かったのか?」「何が足りなかったのか?」と考えるようになる。東北楽天ゴールデンイーグルス監督時代の2008年。野村はチームスローガンを「考えて野球せぃ!」としたが、野村が選手たちに求めていたのは、終始一貫して、「考えること」だったのである。
感情的な「怒り」では、相手の胸に響かない
選手たちが自ら「考える」ようになるためには、「褒める」ではなく、「叱る」ことが最善策だと野村は考えていた。しかし同時に、「叱ると怒るを勘違いしてはいけない」ともいっている。では、「叱る」と「怒る」は一体、どう違うのだろうか? その答えは、実にシンプルだ。生前の野村は、こんな言葉を遺している。
「怒る」は感情、「叱る」は理論――。
「叱る」目的とは、「何が悪いのか?」「何が足りないのか?」を選手や部下に気づかせること。そのうえで、成長を促すことである。叱ったにも関わらず、相手が成長しないのであれば、それは選手や部下のせいではなく、「叱り方が悪いのだ」と野村はいう。
特に指導者がやってはいけないのが、個人的な憂さ晴らしや責任転嫁、八つ当たり、あるいは保身から感情的になったり、怒鳴ったりすることだ。そして、野村はこうした感情や態度のことを「怒る」と述べているのである。感情にまかせて怒りをぶつければ、もちろん選手や部下の成長は見込めるはずもない。
なぜなら、感情による「怒り」は、相手の胸に何も響かないからである。反省する意欲が薄れるだけでなく、無用な反発を招くことになり、最悪のケースでは怒られていることを受け流し、うわべだけ反省したフリをするようになる。そうなってしまうと、監督と選手、上司と部下との信頼関係は破綻し、目標に向かい一丸となって突き進む集団になることはもちろんのこと、円滑な組織運営も望めなくなる。だからこそ野村は、「怒るのではなく叱れ」と説いたのだ。
しかし、そんな野村も「わたしも、感情にまかせて怒ることがなかったとはいえない」と反省しているが、「怒ってしまったな」と思ったときには、素直に反省して「怒るは感情であって、叱るのが理論なのだ」と自分に言い聞かせていたという。
中学生球児の指導から学んだ教訓
先にも述べたように、頭ではよく理解していても、つい感情にまかせて怒ってしまうケースもあった。ヤクルトの監督に就任する直前、野村は「港東ムース」という少年野球チームの監督を務めていた時期がある。このとき、野村は後につながる教訓を得る。
1989年秋、翌年からのヤクルト監督就任が決まった直後のことだ。野村にとっての最後の大会、瑞穂シニアとの一戦は1点を争う緊迫感あふれる試合となった。3回表、ムースのレフト・平井祐二は打球判断にとまどい、走者を三塁まで進めてしまう。そして、犠牲フライで先制点を許してしまった。
結局、試合終盤に逆転して、ムースはそのまま優勝を決めるのだが、この日の試合後、平井少年に対して野村は、「それまで見たことがないほど」感情的に怒りをぶちまけたという。当時の思い出を平井が振り返る。
「僕はレフトを守っていました。でも、目の前にライナーが来て、中途半端な追い方をしてしまってボールをそらし、打者走者を三塁まで進めてしまった……。僕自身の気持ちの弱さが出たプレーでしたが、試合後、野村監督に、『おまえのせいで負けそうになったじゃないか』って怒鳴られましたよ。『もしも負けていたら、どう責任を取るんだ』ともいわれましたね。中学生だったので、その言葉はショックでしたよ(苦笑)」
普段は決して声を荒げることなく、ましてや怒鳴ることのなかった野村が、どうしてこのときは大声を張り上げたのか。のちに平井は悟った。
「たぶん、野村監督のなかにも『これが最後の大会だ』という、期する思いがあったのでしょう。有終の美を飾るために優勝を狙っていたのに、僕のミスが致命傷になりかねなかった。それで、大声が出てしまったのだと、いまなら理解できます」
根底に「愛情」はあるか? 問われるのは上司の資質、本気度
このとき平井に対して、野村は「つい感情的になってしまった」という思いを抱いていたのだろうか? それとも、この一件を反省して、「怒るは感情、叱るは理論」との考え方に至るようになったのだろうか? いずれにしても、のちに「プロ野球の原点は、少年野球にあり」と語るほど、この時期に野村は多くのことを学んだ。
野村は意識的に、「叱る」ことを心がけた。また、本人は「得意ではなかった」と語っているが、先にも述べたように、「褒める」ことの大切さもよく理解していた。そして、「叱る」と「褒める」は実は同じことだともいっている。なぜなら、その根底にはどちらにも愛情があるからだ。
一見すると、「叱る」と「褒める」は正反対の振る舞いのように思えるが、「目の前にいる選手に成長してほしい」という思いは一緒なのだ。しかし、そこに愛情がなければ、前述したように「叱る」は「怒る」となり、「褒める」は「おだてる」となってしまう。真の愛情とは、厳しいだけでも、優しいだけでもないのである。
誰もが生まれながらに持っている理性や知性を尊重し、努力することの大切さに気づかせ、自分から学ぶようにさせること。つまり、「情」を以て「知」を引き出し、「意」へと導くこと。その流れができてはじめて、師弟、上司と部下、先輩と後輩、つまりは教える側と教えられる側の理想的な関係が築かれていくのである。
「怒る」ではなく「叱る」、「おだてる」ではなく「褒める」――。
いずれも、その根底には愛情がある。目の前の人物を心から「育てたい」「育ってほしい」と思えるかどうか? 大切なのは、部下のヤル気や能力ではない。部下を心から愛することができるかどうか? 問われているのは、上司の資質、そして本気度なのである。