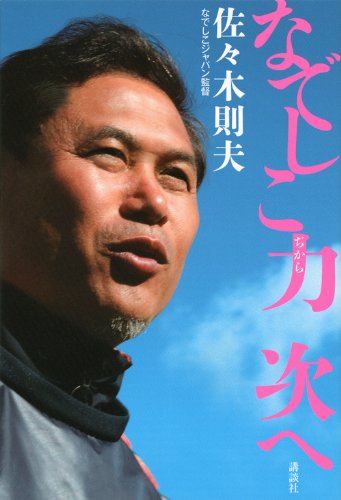ゼロ年代監督たちの共通項
このような選手の自主性、自立性を尊重する姿勢は、落合さんと並ぶ、おそらくゼロ年代を代表する野球監督といえる原辰徳さんにも同様にみられます。2010年の『原点——勝ち続ける組織作り』では、まず選手には高い意思の力と自主性がまず求められると述べています。何よりもまず自分自身でやろう、というわけです。二軍から戻ってきた主力選手に対しては、「頼むよ」ではなく、「よし、やっと来たか。じゃあ、戦ってみろ。出番を勝ち取ってみろ」として迎えるという言及がありますが(171p)、これもまた、選手に対してどんなときでも高い意思の力と自主性を求めるという姿勢の表われだといえます。
原さんにおいて特徴的なのは、選手を尊敬し、自らは出来る限り高みに立たないという姿勢です。「監督というポジションは、あまり高い位置に上ってはいけないな」(149p)と考え、また試合で防げた失敗について話すとき、選手を責めるのではなく、自分を責めることから話を始める(150p)などの言及がそれです。同じ巨人軍の監督ではあっても、かつて川上さんが「『ハイ、ハイ』と選手のいうことをそのまま受け入れてはいけない。立場がちがうのだ」(『悪の管理学』49p)と述べたような、監督と選手の境界を画然と引いて管理統制する、という姿勢とは大きく方向性が異なっていることがわかります。
このような姿勢については、野球解説者の張本勲さんが『原辰徳と落合博満の監督力』のなかで引いている原さんの次の発言により端的に表われています。
「(2度目の監督就任時は原さんも50歳近くなったために、選手と監督の間に:引用者注)壁があるのは仕方がない。それでも、その壁のために選手が言いたくても言えない状況をつくるくらいなら、壁をとっぱらってでも、選手とコミュニケーションするようにしている」(99p)
埼玉西武ライオンズ監督の渡辺久信さんも、『寛容力——怒らないから選手は伸びる』で原さんに近い考えを示しています。同書では、渡辺さんが就任直後の秋季キャンプにおいて「大上段に『俺の方針はこうだ』とぶつけるよりも、まず個別に選手としっかり話し合って、密にコミュニケーションを取る」ほうが、選手との相互理解を図れると考えたことが紹介されています(19p)。渡辺さんはこのように考える根拠について、次のように述べています。
「『それでは監督の威厳が保てないのでは』と考える方もいらっしゃると思います。しかし今の時代の若い子たちは、そういった“上から目線”の権威や押しつけで、思うように動いてくれるような精神構造ではありません」(20p)
この後には、今の若い選手は「怒られ慣れていない」(23p)とする言及もあります。だからこそ、コミュニケーションをとって、「適切な言い方を選び『言葉の力』で選手を理論的に指導していく能力」(24p)が必要だと議論は続きます。