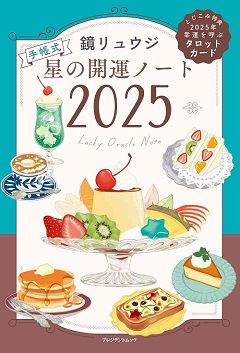占いとジャーナリングの親和性
……と書いてくると、ジャーナリングのブームはあたかも新しい現象のように思えるかもしれないが、実はそうでもない。
僕の専門である占いのジャンルでは、もうずいぶん前から似たようなことをやっているのである。
占いといえば、「この星のもとに生まれたあなたはこんな人」と決定論的に決めつけるものだと思われるかもしれないが、実際にはそうではない。
僕が専門にする占星術にしても、そこで用いるシンボルは実に多義的で、1つの言葉にはおさまらない。
占いは決めつけずに「余地」を残す
「土星」という「凶星」とされた星を考えてみる。
この星は「制限」「ブロック」「恐れ」などを象徴する。この星が「人間関係」の位置にあると、古くは「この人は結婚や人間関係がうまくいかない」と宿命論的に解釈したのだが、今では大きく変化している。その人がこの土星をどんなふうに感じて、どのように自分自身への制限や恐れと向き合っているか、深く考えるようになっている。
手前味噌だが、拙著『占星術の教科書』では、今アメリカでヒットしている「ジャーナル」と似たような書き込み式のワークブックになっている。
自分の土星の位置を調べ、その星の解釈について想いを巡らせたのちに「苦手意識をもっている相手や仕事はありますか」「人より時間をかけなければできないことは何ですか」といった問いかけと書き込みができるスペースを本の中に用意している。
現代的な占いは占い師が決めつけるのではなく、相談者や読者が自分自身と向き合うための余地を残す。いや、この余地こそが現代的な占いの最も重要な核とさえいえるのである。
この本の母体になったのは『星のワークブック』というタイトルで講談社から出したものだが、初版刊行から約20年も経っている。おかげさまで当時から大ヒットし、今のかたちになってからも版を重ねている。