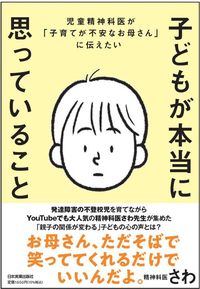「私は傷ついたけど、娘はそうでもなさそう」
長女は自閉スペクトラム傾向があるので、「お友だちと遊んでいても、うまく場になじめていないなぁ」と私から見て思う場面が何度かありました。
子どもというのは、とても素直な生き物です。
長女と友だちのAちゃんとBちゃんの3人で遊んでいたときのことです。
AちゃんがBちゃんに向かって「○○ちゃん(長女のこと)って、なに考えてるかつかめないよね」と長女の前で言ったことがありました。
私もその場にいたので、ちょっぴり悲しく、思わず、「そんなこと言わないで一緒に遊んであげてよー」と言いたくなったのですが、その気持ちをぐっとおさえて、長女の表情を観察しました。
そうしたら、長女は表情をとくに変えることなく、なにごともなかったかのようにその場にいるのです。
それを見て、「あ、私はちょっぴり傷ついたけれど、長女はそうでもないみたい」と冷静にその場をやりすごすことができました。
そして、少し時間がたつと長女もまじえて、みんなで仲よさそうにまた遊んでいました。
あのとき、下手に口を挟まなくてよかったと思った出来事でした。
子どもが傷ついていないか、見極めるのが親の役目
子どもというのは、ときに残酷(に親が聞こえてしまうだけなのかもしれませんね)な言葉を放つことがあり、親である大人のほうが傷ついてしまうこともあります。
でも、そんなときこそ、一度冷静になってお子さんをよく観察してみてほしいのです。
本当にお子さんが傷ついているのか、そうでもないのか。そこを見極めることは親として、とても大切なことだと私は思っています。
子どもにとって、どういう出来事が傷つくのか、それとも、そうでもないのか。子どもが自分にとってネガティブな出来事をどう受けとめて、対応するのか。
「親である自分が傷ついたから、子どもも傷ついたにちがいない、守ってやらないと」と、すぐに子どもたちの中に介入することはおすすめしません。
出来事の自分自身の感じ方、とくにネガティブな出来事であった場合、その避け方や乗り越え方というのは、子どもが自分で見つけ、乗り越えていくことによって、「自分の力で生きていく力」につながるのです。
これは児童精神科医としてというよりも、1人の母親として、わが子の成長をとおしてそう強く感じていることです。