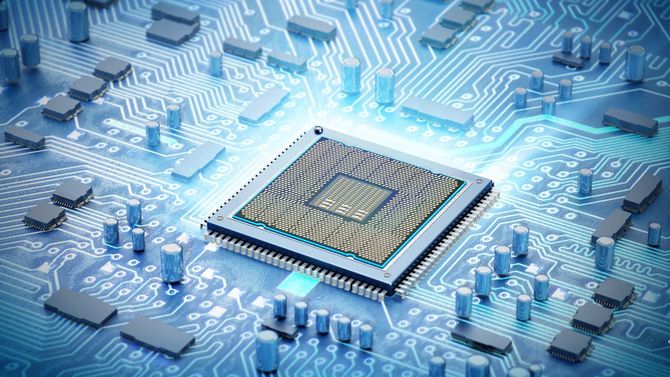外資系ファンドによる東芝へのTOBと非公開化
外資系ファンドと日本企業の関わりという意味で最近とりわけ耳目を集めたのが、東芝へのTOB(株式公開買付け)と非公開化でしょう。
発端は2015年、東芝の長年にわたる不正会計(粉飾決算)が発覚したことにあります。本来なら、ここで上場廃止になるべきでした。実際、もっと少額の不正で上場廃止になった例もあります。2006年にライブドアが有価証券報告書の虚偽記載などによって当時の東証マザーズ市場を追われた件もその一つです。
ところが東芝は上場維持にこだわったため、その後に発覚した米国原発事案の特別損失による債務超過を放置するわけにはいかず、約6000億円の資本増強を迫られました。その手段の一つが、虎の子だった半導体事業の売却。買い手となったのが米国のプライベートエクイティ・ファンド大手のベインキャピタルで、それによって生まれたのが今日のキオクシアです。
しかし、半導体事業売却の時期が2017年3月以降となって東芝の資金調達としては間に合わず、同時進行で増資によって穴埋めする必要に迫られます。それに応じたのが、エリオット・マネジメントやエフィッシモ、サード・ポイントなど複数の外資系アクティビスト・ファンドです。彼らが大株主である以上、その意向に沿った経営をせざるを得ません。
日本には外資系大手に匹敵する規模のファンドはない
この後、結果として余った資金で自社株買いをしたり、取締役を送り込まれたり、経営側が提案した会社分割案を株主総会で否決されたり等々、経営は混乱をきわめます。その状態から脱するため、2023年には国内の投資ファンドである日本産業パートナーズによるTOBの提案を受け入れ、同年末に上場廃止となりました。アクティビストとの資本関係を断ち、日本の企業連合の資本で経営再建をめざそうというわけです。
一連の経緯から、アクティビストは悪者視されがちです。日本のファンドと企業が連携し、沈みゆく大企業を外敵から守ったという図式を歓迎する方もいるでしょう。しかし私から見れば、アクティビストは教科書どおりに利益を追求しただけ。それよりも上場維持にこだわり、事情をわかった上で、彼らに頼らざるを得ないところまで会社を追い込んでしまった東芝の経営陣にこそ問題があると思います。上場維持にこだわらずに2016~17年に非上場になっていれば、今頃は違う形で再建できていたかもしれません。
ついでに言えば、そもそも日本には、外資系大手に匹敵するほど規模の大きなファンドなどが存在しません。だから緊急で数千億円規模の資金が必要となれば、外資系のアクティビスト・ファンドに頼らざるを得なかったのです。
その状況は今も変わっていません。先のTOBにしても、外資系のファンドには売りたくないベクトルが働いていたようですが、日本産業パートナーズ単独では不可能で、複数企業の協力があって初めて成り立ったわけです。