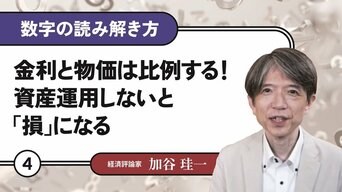※本稿は、菅野久美子『母を捨てる』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
母との「相克の始まり」
いつだって人には、出会いと別れがある。別れがあるのは、恋人や友人だけではない。
自分を生んだ母とも、いつか別れがくる。それは必ずしも、死別という一般的にイメージされやすいものだけではない。
恋人や親友との別れのように、自分で別れを「選択」することだってできる。私は数年前、自ら母を捨て、そして、母と別れた。自分を生み落とした母を捨てることは人生でもっともつらく、身を引き裂かれるような決断であったと思う。
それでも、今の私が自信を持って言えることがある。親との関係がどうしようもなく苦しければ、恋人にさよならを言うように離れてもいいし、捨ててもいいということだ。
まずは、そんな母との衝撃的な「相克の始まり」から振り返ってみたい。
晴れた日の午後、父の仕事部屋で
私が物心ついたとき、それははじめて自分の体と心を認識したときだった。母の胎内から出てきて、まだたった4年ほどしか経っていない、幼稚園児の頃である。私と母との関係は、ここからはじまった。私の一番古い記憶だ。
今も頭に焼きついて離れないのは、西側の窓からサンサンとさし込む太陽の光だ。それは、まばゆいばかりの光で、私と母をいつだって照らしていた。
母と一緒に幼稚園から自宅に帰った私は、黄色の斜めがけバッグを下ろし、紺のベレー帽を脱ぐ。すると、先生やお友だちに見せていた母の満面の笑みが、たちまち鬼のような形相に変化していくのであった。その途端、私の全身が恐怖ですくむ。
「こっちにきなさい!」
母は、私の小さな腕をつかんで、強引に廊下の奥にある部屋に引きずっていく。
そこは六畳一間の父の仕事部屋だった。窓は完全に閉め切られている。それでもカーテンはいつも開いていて、畳は一部だけすすけて黄金色に日焼けしていた。かすかだが、父のつんとした整髪料の匂いが鼻をつく。
部屋の左側には、こたつと座椅子があって、その上にはピンクや黄色など色とりどりの蛍光ペンや色鉛筆、書類が無造作に並んでいた。小学校の教師である父はよく、休日や夕食後はこの部屋にこもっていた。そして、机の上のペンを手に取り、テストの採点や添削に没頭していた。当然ながら平日の昼間にそんな父の姿はない。
母の虐待は、晴れた日の午後で、場所は父の仕事部屋と決まっていた。虐待の理由は、「忘れ物をしたから」「服を汚したから」などだった気がする。しかし、今思うとそれはこじつけに過ぎなかったと思う。
帰宅するなり、私は母から「今日は虐待が起こる日だ」というオーラを嗅ぎ取り、恐怖心でブルブルと震えた。要するに、母の機嫌がすこぶる悪い日というわけだ。朝は笑顔で幼稚園に送り出しても、帰宅すると別の顔を見せることもあった。だから、母の虐待はすべてが予測不能だった。