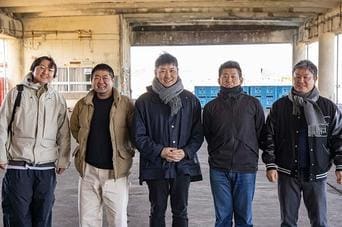一向一揆や島原の乱など、戦国武将はしばしば宗教勢力の台頭に悩まされた。ところが江戸時代に入ると、そうした問題は沈静化する。人気予備校講師の茂木誠さんは「家康は、キリシタンと一部の日蓮宗以外には露骨な宗教弾圧はせず、各宗派の存続を認めた。幕府の行政機関としての存続を保証された仏教各派は、積極的な布教をしなくなった」という――。
※本稿は、茂木誠『「日本人とは何か」がわかる 日本思想史マトリックス』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。
神官の一族につながる信長の家系
室町幕府は、有力守護大名の連合政権でした。足利将軍家の後継者争いが、守護大名の覇権争いと結びついた応仁の乱によって京都は焼け野原となり、幕府は事実上崩壊して戦国時代に突入します。
そんな折、ポルトガル人が伝えた鉄砲の量産に着手したのが、尾張(愛知県)の戦国大名・織田信長でした。
織田家の遠い祖先は、忌部氏という神官の一族です。今川義元を奇襲攻撃して義元のクビを取った桶狭間の戦いの際、地元の熱田神宮で必勝祈願をしていることから、信長が無神論者ではなかったことがわかります。戦乱で荒れ果てた御所を再建したのも、天皇に対する敬意からだったのでしょう。
「天下布武」を掲げて京都に入り、室町幕府を滅ぼした信長に対し、西の毛利氏、石山本願寺、北の浅井氏・朝倉氏、比叡山延暦寺が包囲網を敷きました。その突破口として信長が断行したのが、悪名高い延暦寺焼き討ちです。「宗教」を隠れ蓑に強大な僧兵を抱え、朝廷にもたびたび反抗し、信長の統一を公然と邪魔するに至った延暦寺に対して、信長は堪忍袋の緒が切れたようです。
「仏罰を受けるのでは?」と側近たちが躊躇する中、信長は全山の焼き討ちを命じます。僧兵の多くは妻帯していましたから、婦女子もたくさんいたのです。しかし、信長は容赦なく、「なで斬り」(皆殺し)を命じました。
これを非難する武田信玄からの書状に対し、信長は「第六天魔王」を自称した、と宣教師フロイスは伝えています。第六天魔王とは、仏法を妨げる魔王のことです。