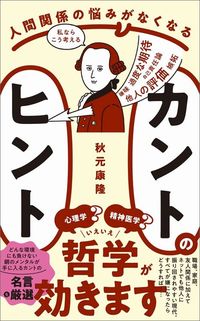愛は「引力」、尊敬は「斥力」
Ak VI 470.
カントは理性的な愛の存在を認めるのと同様に、理性的な尊敬の存在を想定しています。そして、それは相手との距離を保つものとされているのです。この意味での尊敬、すなわち、理性的な尊敬というのは、実際にその人を尊敬するかどうかとは別の話です。(※)
感情的な愛にしろ、理性的な愛にしろ、ともかく愛というのは人と人とを近づけるものと言えます。そのためカントは、それを「引力」と表現するのです。しかし近づくだけでは、実際のところ関係性は成立しません。四六時中一緒にいる(仕事やトイレにまでついてくる)、お互いのプライバシーを一切認めない(メールや通話もすべてオープン)というわけにはいかないでしょう。
このような方向に向かって失敗するのは友人関係よりも、恋人関係の方に多いと思います。友人関係にしろ、恋人関係にしろ、人間というのは両者が近づき過ぎてしまうとうまくいかないのです。
(※)カントは、尊敬について、「たとえ隣人がわずかしか尊敬に値しないとしても、同様にすべての人に対する必然的な尊敬」(Ak VI 448)というものを想定しています。
お互いがある程度の距離を保つ必要がある
私たちは人間それぞれに、人格があり、自由があり、決して他人の持ち物ではないのです。そのことを勘案すると、お互いがある程度の距離を保つことの必要性が看取されるはずです。意図的にその距離を保とうとするのが理性的な尊敬であり、それをカントは「斥力」と表現するのです。
この尊敬に関しては、「普遍化の定式」や「目的の定式」と絡めて説明することもできます。まず「普遍化の定式」との関係で言えば、他者と適度な距離を取るべきこと(束縛しない、プライバシーを守る)ということは、道徳法則に合致すると言えるでしょう。反対にそれを犯すことは道徳法則に反するのではないでしょうか。
また「目的の定式」に鑑みても、他者は目的それ自体として存在しているのであり、その人格は尊重されるべき(つまり、どこまでも立ち入って良いわけではない)ものなのです。
別人格の人間同士がうまくやっていくには、引力としての理性的な愛と、斥力としての理性的な尊敬との適度な均衡が不可欠なのです。
前者は実際に尊敬できるかどうかという感情的な意味であり、後者は実際にその人が尊敬できるかどうかに関わらず、一般に妥当する理性的な意味を持つのです。