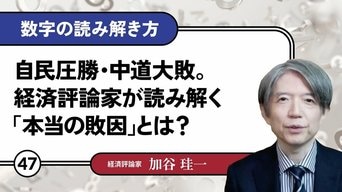1969年の「人類の月面着陸」はどんな体験だったのか
10代の終わり頃に出会い、今でもふとページを開いては、何とはなしに読み始めてしまう一冊の本がある。立花隆さんの『宇宙からの帰還』――私にとって長いあいだ人生の傍らに置いてきた大切なノンフィクション作品だ。
立花さんが1983年に上梓したこの著名な作品は、アメリカの有人宇宙開発に携わった宇宙飛行士たちを取材したものだ。アメリカでは1969年のアポロ11号のミッションによって、ニーム・アームストロングが人類の歴史で初めて月面に降り立ち、バズ・オルドリンがそれに続いた。
「これは人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ」
アームストロングのこの言葉が発せられて以来、アメリカは計12人の宇宙飛行士を月面に送り届けた。
現在、星出彰彦さんが船長として滞在している国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から高さ400キロメートルの「地球低軌道」を周回している。アポロ計画の飛行士たちはその低軌道を離れ、地球から38.4万キロメートル離れた月へと向かった。『宇宙からの帰還』ではそんな冒険的な旅を体験した彼らから、立花さんが「宇宙体験」の内的な意味を聞き取っていく。
宇宙空間に滞在した日本人12人全員にインタビュー
宇宙からの帰還後の飛行士たちの歩んだ道はさまざまだ。キリスト教の伝道師になった者、実業家になった者や政治家に転身した者、長く心を病んだ者もいる。では、そうした彼らの帰還後の人生や価値観に、宇宙体験はどのような影響を与えていたのか。『宇宙からの帰還』における立花さんの関心はそこにあった。
私がこの作品に心を奪われたのは、当時の自分が置かれていた状況も関係しているように今では思う。高校を1年生の時に中退した私は、大検を受けて大学に入るまでの15歳からの3年間のほとんどの時間を、家と近所の個人塾との往復に費やしていた。その頃の自分の世界の狭さを思うと、月への旅という想像を絶するスケールの大きさと、そこから見える光景のイメージの壮大さに魅了されるものがあったのだろう。
作品との出会いから20年ほどが過ぎ、ノンフィクションを書くようになった私は2019年、宇宙空間に滞在した経験を持つ12人の日本人全員にインタビューを行い、『宇宙から帰ってきた日本人』という本を書いた。もちろんそこに込めたのは、ずっと愛読してきた『宇宙からの帰還』への自分なりのオマージュでもあった。