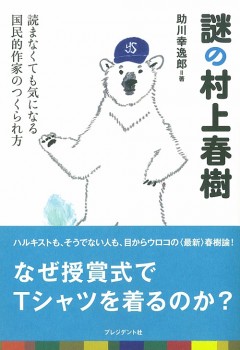嬉々として「ハルキ節」を歌う
事実、この短編集のどの作品を見ても、過去の春樹の小説で見かけた憶えのある表現やディテールに満ちています。
冒頭に置かれた『ドライブ・マイ・カー』は、妻と死別した中年の俳優が、妻の晩年の浮気相手に、仕返ししようとして近づく話です。そこで語られる演技論は、『ダンス・ダンス・ダンス』の五反田君――「僕」の同級生だった二枚目俳優――が口にするそれを思いおこさせます(どちらの議論においても、演技は「自分と別の存在になること」のメタファーになっています)。
「イエスタディ」では、幼なじみがそのままカップルになった20歳のふたりに、谷村という語り手がかかわっていきます。カップルの女性のほうが大学で専攻しているのは、フランス文学です。また、『ノルウェイの森』のワタナベは、緑から「ハンフリー・ボガートみたいな話し方をする」といわれる男でした。『イエスタディ』にも、「決めの台詞を口にしすぎることも、僕の抱えている問題のひとつだ」というフレーズが現れます。この作品はあきらかに、『ノルウェイの森』の「セルフパロディ」です(どちらの作品も、タイトルがビートルズの曲名からとられています)。
『独立器官』は、50歳を過ぎてはじめて真剣に恋をし、相手に裏切られて破滅する美容整形医の物語です。美容整形医の秘書として、身ぎれいで有能なゲイの男が登場します。春樹の愛読者なら、『1Q84』のタマルを思いうかべたくなるキャラクターです。
『シェエラザート』は、31歳になる羽原という男の視点から物語が語られます。彼は、某地方都市にある「ハウス」に潜伏している身です。羽原より4つ年上の主婦――羽原は彼女を、「シェエラザート」というあだ名で呼んでいます――が週2回、支援のために「ハウス」にやってきます。『1Q84』で、「さきがけ」の教祖を暗殺したあとの青豆が置かれていた境遇に、羽原のそれは酷似しています。羽原と青豆は、年齢もおなじです(そういえば、青豆に暗殺を依頼したマダムの経営する、ドメスティック・ヴァイオレンスの被害者収容施設も「ハウス」と呼ばれていました)。
『木野』の主人公は、妻の浮気をきっかけに離婚して職も辞め、青山でジャズ・バーをはじめた木野という男です。やがて彼の身に異変が起こるのですが、その先ぶれとして、可愛がっていた猫がいなくなります。この展開は、『ねじまき鳥クロニクル』を連想させます。邪悪なものの侵入におびえながら、懸命に持ちこたえようとする主人公を描いて終わるところは、『眠り』という短編にそっくりです。
最後の『女のいない男たち』は、かつて恋人だった女性が自殺した、という連絡を、語り手の男性が受けるところから始まります。彼がつきあった女性のなかで、自殺者はこれが3人目であると語られますが、これも『ノルウェイの森』の主人公を連想させる設定です。
『1Q84』あたりから、春樹の小説には、過去の自作とおなじ表現、モチーフが目立つようになってきました。さすがの春樹も、作家として曲り角にきているのではないか。そんな疑いをもったのも、一度や二度ではありません。しかし、今回の短編集では、「いかにもハルキっぽい小説」を書くことを、むしろ春樹自身がたのしんでいるように映ります。