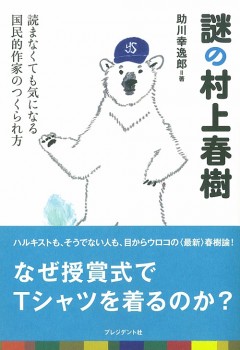今年4月に発売され、当然のごとくベストセラー街道を独走した村上春樹9年ぶりの短編集、『女のいない男たち』。賛否がはっきりわかれた1年前の長編『色彩をもたない多崎つくると、彼の巡礼の年』に比べるとコアなハルキストにもそうでない人にもすんなり受け入れられた感がある。しかしこの作品こそ、「ニュー村上春樹」の出発点となるだろうと『謎の村上春樹』の著者、助川幸逸郎氏は分析する。そのこころは……。
「女のいない男たち」ばかり書いてきたのに
『女のいない男たち』は、村上春樹にとって9年ぶりの短編集です。彼の著作としてはめずらしく、この本には「まえがき」があり、そこにはこんな一節が見えます。
本書のモチーフはタイトルどおり「女のいない男たち」だ。(中略)いろんな事情で女性に去られてしまった男たち、あるいは去られようとしている男たち。
どうしてそんなモチーフに僕の創作意識が絡め取られてしまったのか(絡め取られたというのがまさにぴったりの表現だ)、僕自身にもその理由はよくわからない。そういう具体的な出来事が最近、自分の身に実際に起こったわけではないし(ありがたいことに)、身近にそんな実例を目にしたというわけでもない。ただそういう男たちの姿や心情を、どうしてもいくつかの異なった物語のかたちにパラフレーズし、敷衍してみたかったのだ。
私は、これを読んでびっくりしました。彼のデビュー作である『風の歌を聴け』は、恋人に自殺されてしまった学生が主人公です。『羊をめぐる冒険』は、妻と主人公の別れのシーンで幕を開けます。最後にヒロインが自殺する『ノルウェイの森』。主人公が失踪した妻を取りもどすまでを描いた『ねじまき鳥クロニクル』。春樹はくり返し、「女性に去られてしまった男たち、あるいは去られようとしている男たち」の物語を紡いできました。
にもかかわらずここでは、「女のいない男たち」というテーマに、今になって取りつかれたかのように書かれています。自分のしてきたことにそこまで無頓着な人物は、職業小説家としてやっていけないはずです。私はこの「まえがき」を最初に目にしたとき、春樹がどういうつもりでこれを誌したのか、理解できませんでした。