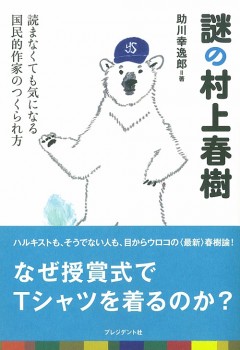いまでかつてないストレートさ
どうしてここでの春樹が、嬉々としてハルキ節を歌っているように見えるのか。それには、いままでの彼にはなかった「執筆態度の率直さ」があずかっていると、私は考えます。
櫻井瑛子。妙なかたちの鼻をした、ひょろりと背の高い女の子で、親が大きなゴルフ場を経営している。気取っていて、性格もあまり良くない。胸もほとんどない。ただし昔からテニスだけはうまくて、よく大会に出ていた。できることなら二度と会いたくない相手だった。(『イエスタディ』)
春樹ではなく、村上龍の小説に出てきそうな「放言」です。春樹の小説では、「胸が大きいこと」が「美徳」として語られることはこれまでにもありました。しかし、「胸がないこと」を、女性を非難する材料として語り手が口にのぼらせることは、なかったように思います。
小説の語り手の見解と、作者自身のそれはあくまで別ものです。とはいえ両者は、しばしば混同されます。春樹は、そのことに対する警戒心が強いタイプの書き手でした。語り手や視点人物が、極端な意見を留保もなしに口にする。そういう状況があらわれることを、春樹は周到に避けてきました。
このため、春樹作品のほとんどは、「落ち度」を持たない人間の目をとおして語られています。そういう小説は、語り手や視点人物に自分をかさねながら読んでも、やましい気持になりません。〈僕〉と共感するうえでのこの「敷居の低さ」が、春樹の人気をある面では支えていました。
同時に、作品の「のぞき窓」となる存在から「落ち度」を排そうとするあまり、煮えきらない印象を受けることも春樹の作品にはありました。『女のいない男たち』に収められた6つの作品は、その種の煮えきらなさを微塵も感じさせません。
「読者から自分に批判の矢が飛んできても、作中人物に言わせたいことは率直に言わせる」
――作者のこうした姿勢が、「のびのびと〈らしさ〉を全開にしているムード」を生みだしているわけです。ここでの春樹の、空振りをおそれずにバットを強振していくようないさぎよさには、声援を送りたくなります。