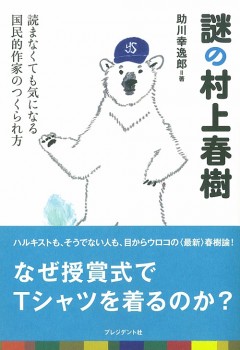「対話」の行きかう小説
語り手や視点人物に「落ち度」があること――このことを「解禁」にしたことの意義は、それのみにとどまりません。
物語を切りひらく立場にある人物が、他人のことばによって根源的に変わることは、春樹の小説ではほとんどありません。「落ち度」のない人物は、実際的なアドヴァイスを必要とすることはあっても、生きかたそのものをだれかに正される筋合はないからです。
「落ち度」のある語り手や視点人物が登場する『女のいない男たち』では、この点にも変化が生じています。
『ドライブ・マイ・カー』の主人公は、妻を寝取っていた男・高槻を酒席に誘います。酔わせて弱みを吐きださせ、それをネタに高槻を陥れようという心算でした。相手がこちらを思いやることばを投げかけても、主人公は、内心の冷ややかな感情を変えません。
高槻は、主人公より10歳ほど齢下の、才能にとぼしい俳優です。彼はしかし、あるタイミングで、らしくもない深いことばを口にします。これを聴いて、主人公の家福は驚きます。
高槻という人間の中のあるどこか深い特別な場所から、それらの言葉は浮かび出てきたようだった。ほんの僅かなあいだかもしれないが、その隠された扉が開いたのだ。彼の言葉は曇りのない、心からのものとして響いた。少なくともそれが演技でないことは明らかだった。それほどの演技ができる男ではない。家福は何もいわず、相手の目を覗き込んだ。高槻も今度は目を逸らさなかった。2人は長いあいだ相手の目をまっすぐ見つめていた。そしてお互いの瞳の中に、遠く離れた恒星のような輝きを認めあった。
ほんとうの意味での「対話」は、相手のことばによって、自分の考えの根本が組みかえられる可能性がないと成立しません。春樹の主人公は、物語の幕開きからずっと「正しい人」であるのがふつうです。必然的に、春樹の文学は「対話」に乏しいということになります。
右に引用したくだりにおいて、高槻の発言を耳にした家福は、相手を陥れようという「邪念」をなくしています。『ドライブ・マイ・カー』は、家福という「正しくない」主人公を登場させた結果、春樹にしてはめずらしい「対話の行きかう小説」になったのです。
『独立器官』では、主人公の渡会と語り手の谷村が、不完全な人間のあいだにおいてしか成りたたない、ダイナミックな「対話」を交わしています。とくに、みずからの嫉妬心や理解力不足を、自覚せずにさらしている谷村は、これまでの春樹小説には見られなかったタイプの語り手です。