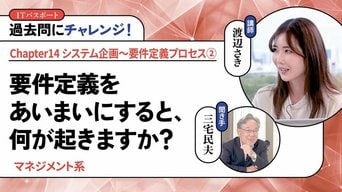※本稿は、平尾喜昭『狙って売上を伸ばすデータ分析の思考法』(クロスメディア・パブリッシング)の一部を再編集したものです。
他社と競争しても、市場が伸びない
【平尾】伊藤園さんと言えば、「お~いお茶」というナンバーワンブランドで有名です。御社でデータサイエンスを取り入れるうえでは、どのような課題感があったのでしょうか。
【志田】当社では、1985年に世界初の「缶入り緑茶」を発売。これを前身に、89年には「お~いお茶」が生まれました。90年代はとにかく緑茶市場が伸びた時代で、われわれは緑茶の魅力を発信していればよかった。ところが2000年代半ばから各社が参入してきて、2010年代はブランド間競争の時代でした。
でも、ふと気づいたんです。がむしゃらにやってきたけれど、市場がまったく伸びていない。振り返ってみると、2005年が緑茶飲料市場のピークでした。そこから10年間、各社がものすごい予算を投じてブランド間競争をしていたのに、市場はずっと停滞していた。そこで初めて、「俺たち、何のためにやってんだ?」と振り返り始めたわけです。
「畑から育てている」とアピールしても…
【平尾】なるほど。「顧客のため」ではなく、ブランド間競争に執着してしまっていたということですね。そこからどのように変革していったのでしょうか。
【志田】われわれの強みは、何と言っても「畑から育てている」ことです。市場の茶葉の4分の1を仕入れ、2500ヘクタールもの契約茶園を持つ。茶業界自体を背負っているという自負もありました。そこで、改めてこの強みと“ものづくり”の精神を伝えることに注力したんです。テレビCMでは茶畑を映し、鮮度へのこだわりを伝えていきました。
ところが、マインドシェアは全然上がらず、結局、価格競争に巻き込まれていく。最初は「伝え方が下手なんだ」という話でしたが、そうこうするうちに、お恥ずかしながら気づきました。「一生懸命に自分たちの価値を伝えても、誰も興味を持ってくれないんじゃないか」と。
この閉塞感のある状況を、どういう仮説を持って打破していくかが、当時の課題でした。