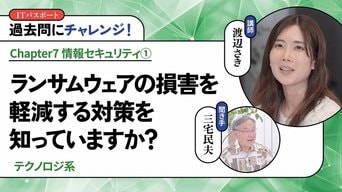人形に「人格」を感じた瞬間
――濱野さんは取材したドール・ユーザーからラブドールを借りて生活したそうですね。一緒に暮らしてどうでしたか。
「ジャッキー」という名前の等身大の人形を借りたのですが、彼女を目の前にしたとき、私はまず「怖い」と感じました。ただの物ではなく、得体の知れないものがそこにいるような感覚があったからです。なんというか、死体に近い不気味さがありました。
あまりの存在感ゆえに、私は反射的に「この娘は働き詰めで疲れていて、休む場所を探していた。そこに私がベッドを提供した。ここでいくらでも寝て、疲れを取る機会にするといい」という「物語」を作り出したのです。それは、人形に物語を当てはめるのではなく、「物語が勝手に立ち上がってしまう」ような感覚でした。
ほかにも、これまで男性から性的に利用されてきたであろうジャッキーの唇に触れたときに、不意に「かわいそう」と呟いてしまったことがありました。こんな反応をしたことに自分でも驚いたのですが、私は、人形の存在を「怖い」と感じたからこそ、物語を当てはめることで「生きた存在」として関係性を構築せざるを得なかったのかもしれません。
この経験から、私は等身大人形という存在自体が人間に「物語」を立ち上げさせる力を持っていると考えるようになりました。おそらく、前回の記事で紹介したデイブキャットや近藤さんなどのドールの夫たちも、私に起きたような出来事を毎日積み重ねて、人形に詳細なプロフィールや人格的な奥行きを与えているのではないでしょうか。
たとえば、ドールの夫であるデイブキャットは、パートナーではなく「セックス専用のラブドール」を購入したことがあったのですが、人格のない「ただの人形」として扱えたのは3週間程度だったそうです。デイブキャットのように等身大人形と結婚し、人形に人格を与えることが当たり前になっている人間にとっては、人形に人格を感じることは当たり前のことなのです。