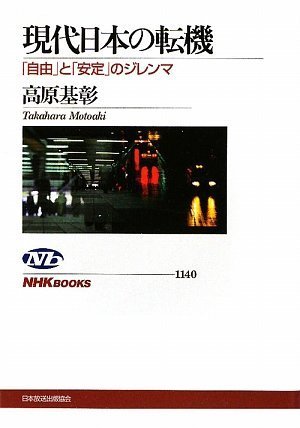本書は、これまで日本が避けてきた非常に重いテーマを真正面から取り上げている。石油危機に端を発した1973年の“転機”により、「20世紀システム」とM・ウェーバーらがいう意味での「官僚制」からなる「近代」は終わってしまったと結論づけ、「代わりに立ち現われるのは、先進国も途上国も、そしてその内部の諸個人も自助努力を求められ、そして脱落すれば『置いてきぼり』をくらう、『新しい近代』である」(77ページ)と指摘する。90年にバブルが崩壊し、それを克服するかにみえた小泉構造改革も、リーマン・ショックで幻想だとわかり、ますます閉塞感が強まった。
社会学者が著した本書は、現在の経済現象の水面下で何が起きているのを理解するうえで多くの示唆に溢れている。たとえば、先進国の金利が74年にピークをつけて一斉に低下傾向に入ったのは、「近代」の終焉と大きな関係があるということを教えてくれる。また、90年代に「『超安定社会』という自画像を支えていた3つの要素がこの時期に共通して、終焉」(204ページ)したという指摘からは、なぜ日本の一人当たり賃金が同じ時期にピークを迎え、その後下がり続けるのかが理解できる。

とりわけ、「バブル崩壊後の日本に起きたこととは、広汎な『国民との約束事』の崩壊であり、旧来の体制の正当性の危機だった」(253ページ)という視点は、現在の日本の政治・経済を考える際に非常に重要だ。著者がいう旧来の体制とは、高度成長、日本的経営、そして日本型福祉社会の3要素からなる「超安定社会」であり、「人々は、この体制の形成に参加したという意識もなければ、その崩壊を後押ししたという意識もなかった」(254ページ)という指摘からは、自民党がこのことを認識していなかったゆえに、今回の総選挙の民主党大勝に繋がったのではと思えてくる。一般にいわれるような解散のタイミングなどを巡る自民党の戦略ミスなどではなく、「73年の転機」に気づかなかったというはるかに根深い問題なのだ。同時に、ダム建設を巡る地元住民と新政権の対立をみると、マニフェスト選挙が定着してきたとはいえ、あまりに個別事象にこだわりすぎていないかと思える。本来なすべきは、包括的な「国民との約束」であるといえよう。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント