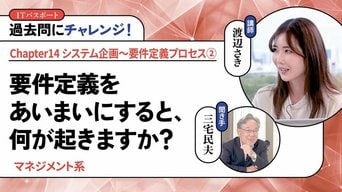著者の山川静夫氏は元NHKの看板アナウンサーだ。紅白歌合戦の司会を14回も務めたことで有名だが、実は30冊近い著作を誇る古典芸能評論家でもある。
本書は、著者の歌舞伎狂いを語るような自叙伝的な趣があるのだが、じつは歌舞伎という日本固有の文化を楽しむための必読書に仕上がっている。
歌舞伎関係の本というと、ほとんどが入門書であり、いかに歌舞伎が難解な芸能ではないかを強調するものが多い。あらすじの紹介や用語の説明に終始する本も多く、逆に歌舞伎は知識なくしては楽しめないような仕立てになっていることが多い。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント