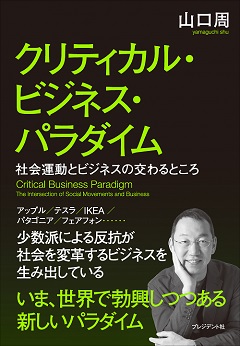※本稿は、山口周『クリティカル・ビジネス・パラダイム 社会運動とビジネスの交わるところ』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
SNSでデモをするZ世代が「世界10大リスク」に
社会運動の数は近年、劇的に増加しています。ハーバード大学行政大学院で社会運動に関する研究を行っているエリカ・チェノウェスは、近著『市民的抵抗』において、2010年から2020年の10年間は、記録に残っている歴史上のいかなる10年間よりも多くの非暴力的な社会運動が起きたこと、そして特に、21世紀の最初の20年間で起きた社会運動の数は20世紀全体の100年間に起きた数よりも多かったこと、を指摘しています。
つまり、21世紀に入ってから、社会運動の数は激増しているのです。
私たちの世界は、かつてないほどに社会運動による揺さぶりを受けており、これが不確実性を高める一つの要因にもなっています。ニューヨークに本拠を持つ地政学リスクを専門に扱うコンサルティング・ファームのユーラシア・グループは、2023年の世界十大リスクの一つとして「ロシアに関連する安全保障危機」や「習近平氏への権力集中」といった地政学的な要素と並んで「SNSをフル活用して社会変革に挑むZ世代」を挙げています。
自分のためではなく、他者のために訴えている
さて次に「質の面」について考えてみましょう。先述した通り、20世紀の半ばまで、社会運動のほとんどは、運動に関わる当事者の物質的・経済的困難の解消を目的にしていました。ところが近年、特に先進国における社会運動は、物質的・経済的困難の解消を目的とするよりも、環境問題の解決や社会的平等や公正の回復を目的とする運動が主流となっています。
それはたとえば、スウェーデンのアクティヴィスト、グレタ・トゥーンベリ氏によって始められた「Fridays For Future」であり、一連のLGBTQ+の権利を守るための社会運動であり、人種差別撤廃を求める「Black Lives Matter」などの社会運動であり、性的暴力の告発を拡散させた「Me Too ムーブメント」などです。
言うならば、これらの社会運動は、運動の当事者の問題ではなく「遠くの他者」や「未来の他者」の問題を解消するための運動に変わってきているのです。
古代以来、歴史を通じてこれまで主流だった「自分のための運動」は、21世紀に入ってから「他者のための運動」に変わってきている。なぜ、このような変化が起きているのでしょうか? 理由は大きく五つあると考えられます。