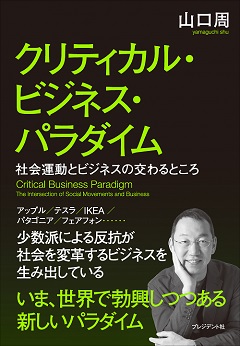国の問題や経済的困難を超えたテーマへ
一つ目が経済的発展による物質的不足の解消です。特に先進国をはじめとして、基本的な物質的ニーズが満たされるようになり、人々はより公共的・社会的な問題に焦点を当てるようになりました。
二つ目が、グローバリゼーションによる国際的な認識の高まりです。グローバリゼーションの進展により、かつてと比較して、個別の国で高まった問題意識が、国境を越えて共有されるようになりました。気候変動のような地球規模の問題は、特定の国や地域だけの問題ではなくなっています。
三つ目に、メディアとコミュニケーションのあり方の変化が挙げられます。特に、一般市民が世界に向けて情報発信できるプラットフォームであるソーシャルメディアの台頭は、個人が広範囲にわたる問題について把握し、意識を高め、行動を起こすきっかけを提供しています。
現在、世界では53億人の人がインターネットにアクセスできる環境にあり、うち50億人がSNSを利用しています。世界全体の個人が、別の地域にいる無数の個人とつながるようになったことで、現代の社会運動は、物質的な不足や経済的困難を超えた、より幅広いテーマに対処するようになっています。社会の発展と共に、人々の関心や価値観も進化しているのです。
「不可逆なもの」という共通点
四つ目が、教育による意識の向上です。特に現代の若い世代は、以前の世代よりも高い教育水準を享受しており、世界的な問題についての認識と理解が深まっています。教育を通じて、環境問題、社会的正義、人権などについて学び、それらに対する共感を育んでいます。
そして五つ目、何よりも大きいと思われるのが、価値観の変化です。様々な調査が、物質的な豊かさよりも、社会的な意義や個人のアイデンティティ、倫理的な価値を重視する傾向が若い世代には見られることを報告しています。これは、社会運動が個人の物質的な不足や経済的な困難から、広範な社会的、環境的な問題へとシフトする大きな要因となっています。
ここまでに挙げた五つの要因には共通した特徴があります。それは、これらの変化が不可逆なものだ、ということです。もし、これらの要素によって「共感力のある人々」が増加し、その増加がクリティカル・ビジネスの台頭の駆動エンジンになっているのであれば、このトレンドは長期にわたって継続すると考えた方が良いということになります。