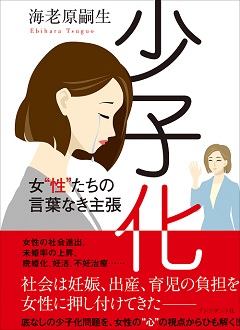「女性が仕事をすると出生率が下がる」のウソ
【海老原】権丈先生がすごいのは、血の通わない経済学の定説に対して、しっかりと反論をして、「より現実に近い」話をして下さるところですね。たとえば、「女性が仕事をすると、出生率は下がる」なんて話が、かつては統計データの分析から語られていました。でも、そんな「常識」が、ある時期から綻びを見せだした。数字しかいじっていないダメな学者は、この変化を説明できませんでしたね。
【権丈】今回海老原さんが、豊富なデータを用いて、女性のキャリアや生き方を応援しようという本をお書きになられたこと、とても嬉しく思っています。「女性が仕事をすると、出生率が下がる」ということについては、必ずしもそうとは言えない、要は制度、政策次第ということを最初にお話ししたいと思います。
女性が働く国のほうが、出生率が高い
【権丈】先進諸国で国際比較をすると、1970年代には女性の労働力率が高い国で、出生率が低い、という負の相関がみられました。今に続く意識は、この時代に作られたとも言えます。ところが、対象とする国を固定して1980年代の関係を見ると、負の相関が崩れ始め、1990年代になると、この関係が逆転しました。
その背景には、女性の教育水準が高まり彼女たちの社会進出が先行した国々では、それに対応して、社会も企業も、仕事と育児の両立をしやすい環境を整備するようになったことがありました。制度を整えた国々では出産・育児に伴う機会費用が減少して出生率が回復した一方、女性の社会進出が遅れている国々ではそうした環境整備が不十分であったために、1990年代には、女性の労働力率が高い国のほうが出生率も高くなるという関係になったわけです。
この相関関係の負から正への転換は、日本でも注目されるようになり、少子化と働き方の関連が認識され、仕事と育児の両立支援や、ワーク・ライフ・バランスに力を入れるきっかけになりました。