老化のスピードが決まる3大要因とは
顔にシワが増えてきた、階段を上るとすぐに息が上がってしまう……。日常のさまざまなシーンで感じる「老化」は、諦めるしかないと思っていませんか。ところが近年、老化のメカニズムについての研究が進み、120年以上生きることさえ可能になると考える研究者も増えています。世界中の第一線の研究者が集う、健康長寿をテーマにしたハーバード大学のシンポジウムでは、概して「医学の進歩で、ヒトはいずれ150から180歳まで生きられるようになる」という結論になります。
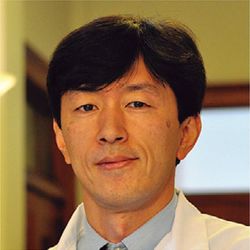
根来秀行 Hideyuki Negoro 医師・医学博士。東京大学大学院医学系研究科内科学専攻博士課程修了。ハーバード大学医学部客員教授、ソルボンヌ大学医学部客員教授、東京大学客員上級研究員ほか。アンチエイジング研究の第一人者。
とはいえ、医学の力で老化を止めて寿命を延ばすことは、がんなどの深刻な病気を引き起こすリスクが伴うため、すぐに実用化されることはないでしょう。一方、生活習慣を改善することで、細胞内にある「テロメア」という「命の回数券」とも呼ばれる遺伝子の構造を節約し、老化を予防できることがわかりつつあります。テロメアについて、詳しくは後述します。
「大人になってから起こる生理機能の衰えにより、さまざまなストレスに対する適応能力が低下すること」、これが老化の一般的な定義です。たとえば、年を取ると呼吸機能全般が低下して、運動をすればすぐ息が上がるようになり、病気をすれば呼吸器系の疾患が生じやすくなります。さまざまなストレスに適応しにくくなるわけです。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント





