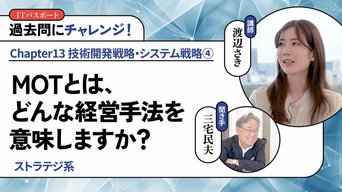※本稿は、尾原宏之『「反・東大」の思想史』(新潮選書)の一部を再編集したものです。
慶應大学をつくった福沢諭吉の東大批判
明治初頭、福澤はすでに「官の学校」の長所として「自から仕官の途に近し。故に青雲の志ある者は殊に勉強することあり」と述べていた(「学校之説」)。
帝国大学への進学はエリートの地位と制度的に直結しており、立身出世を求める若者にとって抗いがたい魅力を持つ。一方の私学は兵役の猶予すら得られない。
官学の隆盛と私学の衰退は、明治10年代後半以降の福澤がリアルタイムで感じ続けた危機だったのである。
このあたりから福澤の官学批判はエスカレートしていく。前に触れた1887年の論説「国民の教育」では、「人民が私の目的にする其教育に公けの金を使用するは正則にあらず」と主張した。
教育とは、子供を成功させたい、立身出世させたいという親の「私情」によるもので、そもそも「公共の資金」を支出する対象ではない。ただし、なにも教育しないのは「社会全体の安寧」に問題を生じるので、読み書きと多少の算術までは政府が負担する。
それ以上は親が負担すべきで、政府が「高尚専門の教育」に費用を出すのは「余分の世話」である。
この福澤の主張は原則として高等教育に公金を投じることを認めないので、必然的に帝国大学をはじめとする官学は廃止または民営化されるのが望ましい、という結論になる。
私学のレベルが低いのは政府のせい
実際、これに続く論説「教育の経済」では、官学を廃止して私学に教育を委ねるべきと主張した。その際に障害となるのは、私学の教育レベルが低いという世間の評判である。福澤は、驚くべきことにその悪評をなかば認める。だが、それは政府の責任だという。
私学のレベルが低いのは単純にお金がなくて高度な教育ができないからである。なぜお金がないのか。学生から高い授業料を取ることができないからである。なぜ高い授業料を取れないのか。「授業料の最も低くして課程の最も高き官立学校なるものあればなり」。
官学が安い授業料で最高度の教育を提供しているので、それより程度の低い私学で高い授業料を取るわけにはいかない。税金が原資である「国財」を使って最も高度な教育を最も安い授業料で提供している官学が諸悪の根源なので、これを廃止すれば私学しか存在しない世界になる。
そうなれば、私学は堂々と授業料を値上げして資金を集め、高等の課程を設置し、素晴らしい人材を育成できる。
要するに、官学が政府の力をバックに不当な安値でよい品物を叩き売るダンピング行為をするから、私学の発達が阻害されるというわけである。