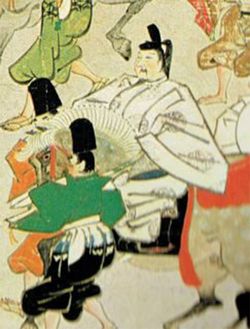娘も息子も異常なまでに昇進する
そこで道隆は「三后」を退位させる代わりに、奇策に打って出た。先述の「中宮」は「皇后」、または「三后」全体の別称だったのだが、別称があるのをいいことに、「中宮」というあたらしい后の枠を創って、その座に定子を就けることに思い至り、それを強引に推し進めたのだ。
山本淳子氏はこれを現代日本に置き換え、「『総理大臣』に『首相』という異名があることを使用して、現総理とは別にもう一人首相が立つ」とたとえている(『道長ものがたり』朝日選書)。
また、長徳元年(995)正月、次女の原子も皇太子の居貞親王(のちの三条天皇)に入内させたが、道隆が地位を引き上げたのは娘だけではなかった。いうまでもなく、息子の地位も飛躍的に上昇させた。
すでに第14回で、長男の伊周(三浦翔平)が弱冠17歳にして、天皇の秘書官長である蔵人頭に抜擢されたことが描かれた。伊周はその4カ月後の正暦2年(991)1月には、大臣とともに政に参画する参議に就任して、太政官の高官である公卿に列し、その年のうちに従三位権中納言、翌年には正三位権大納言になった。
そして正暦5年(994)、道長の舅である左大臣の源雅信(益岡徹)が没すると、叔父の道長らの頭越しに内大臣に昇進。このとき伊周はまだ21歳で、権大納言に据え置かれた道長は、8歳年下の甥に官職で追い越されてしまった。
また、伊周の5歳年下の弟であった隆家もまた、若すぎる昇進を遂げていった。正暦5年(994)8月には、16歳で従三位になって公卿に列した。記録されているかぎり、平安時代になってから最年少の公卿だった。翌長徳元年(995)5月には権中納言に任ぜられている。
権力の絶頂期に患ったふたつの病
しかし、道隆のあまりに強引な身内びいきは、周囲の不満を募らせることになった。なかでも一条天皇の生母であった東三条院、すなわち、ドラマでは吉田羊が演じている道隆の同母妹、詮子の反発を買い、そのことが中関白家のその後に、大きな負の影響をおよぼすことになった。
伊周が21歳で内大臣になり、隆家が16歳で公卿になった正暦5年(994)には、すでに疫病が都に蔓延していた。『栄華物語』は「いかなるにか今年世の中騒がしう、春よりわづらふ人々多く、道大路にもゆゆしき物ども多かり〔どうしたことか、この年は世の中が騒然とし、春から病にかかる人が多く、都の大路にも忌まわしいもの(遺体のこと)がたくさんある〕」と書かれている。
このときの疫病は疱瘡、現代でいう天然痘で、『日本紀略』の正暦5年「七月条」には「京師の死者半ばに過ぐる。五位以上六十七人なり」と記されている。都では人口の半分が死亡し、五位以上の貴族だけでも67人が死んだというのだ。これが道隆を襲うことになる。
だが、大の酒好きだったと伝わる道隆は、もともと飲水病、つまり現代の糖尿病も患っていた。前出の山本氏は、「本人にはしばらく前から自覚症状があったのではないか。その焦りがあからさまな人事に直結したと思えてならない」と書いている(前掲書)。
疱瘡と飲水病のどちらが致命傷だったかはわからないが、長徳元年(995)4月10日、道隆は死去してしまう。