安藤忠雄と千利休
本書が導出している住宅の10の「アーキタイプ」をみておこう。
II.清里ペンション派:西洋のオウチのコピー
III.カフェバー派:演劇の舞台空間のコピー
IV.ハビタ派:モダニズムへの憧れ
V.アーキテクト派:建築家との知的交流への憧れ
VI.住宅展示場派:「住宅の人生化」の受け入れ
VII.建売住宅派:日本の「持家信仰」の物象化
VIII.クラブ派:「理想の家庭」のコピーのコピー
IX.料亭派:抽象化された「高級な和風」への憧れ
X.歴史的家屋派:家を建てる「恥ずかしさ」の解決
具体を抽象レベルへ引き上げ、その位置エネルギーを使って具体へと降りる。その結果、まるで異なった文脈に置かれた2つの具体の間に概念的な補助線が引かれる。これが新しい理解や洞察をもたらす。こうしたメタファーの醍醐味を5番目の「アーキテクト派」を例にとってみてみよう。
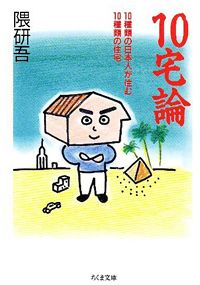
[著]隈 研吾(筑摩書房)
アーキテクト派の住宅に住む人々は、建築家に自分の家の設計を頼む。そもそもなぜ建築家に頼むのか。その建築家の作風が気にいったからではなく、むしろ「建築家との知的な交流」に意味があるというのが著者の見解だ。知的にソフィスティケートされた情報を、メディアではなく生身の人間から得る。ここにアーキテクト派の真の欲求がある。建築家に設計を依頼すれば、必然的にその建築家と親密につき合うプロセスがついてくる。「デパートの外商の人間では多少物足りないなという奥方も、建築家との打ち合わせ、世間話、芸術談義からは充分な満足を得ることができる」のである。アーキテクト派の根本にあるのは、妻の知的欲求不満というオチになる。かのフランク・ロイド・ライトも設計した住宅のクライアントの妻と、何回もスキャンダルを起こしているという。
ここで話はいきなり戦国時代の茶人に移る。現代の建築家と同じように、彼らは知の交通を司る役割を果たす者として戦国大名に重んじられた。茶人と交わることで、大名たちが新しい情報にアクセスでき、ここに大きな意味があった。これはそのまま現代の建築家とアーキテクト派の関係のメタファーになっている。建築家に住宅を建てて欲しい人の欲望を、戦国時代の大名の欲望に重ねることでその本質が見えてくる。
もともと茶人は中国の文化や、情報の紹介者として珍重されていた。ところが、千利休は中国指向を否定した。ここに利休のオリジナリティがあった。彼は日本の陶磁器の価値を認め、それまで黙殺されていた「日用雑貨」の類いでも、自分の目にかなったものには積極的な価値を認めて、茶会でもバンバン使い始めた。ここで利休が新たに提唱した価値判断の基準が、「わび」「さび」だった。「利休の反転」である。この反転は、一面では華美で高価な唐物をむやみにありがたがっていた成り上がり大名たちに対する痛烈な批判だった。
こうして建築から茶の湯に具体の文脈を移したうえで、議論は再び建築に戻ってくる。戦国時代に茶の湯の世界で利休が行ったような反転を、現代の建築の世界で行う。そこに安藤忠雄の仕事の本質がある、と著者は指摘する。利休以前の茶人が基本的に唐物の目ききであり、中国文化の紹介者であったように、安藤以前の日本の住宅建築家は、基本的に唐物の目利き――すなわち西洋の進んだ住生活の紹介者にすぎなかった。そこに安藤忠雄が現れる。彼は有名な「住吉の長屋」のようなコンクリート打放しの小空間を提示して、新しいわび、さびの美学を呈示した。建築の世界における「利休的反転」である。
しかも安藤忠雄の建築は、利休の「わび・さび」がそうであったように、ちっとも貧乏くさいものではなかった。なぜなら、利休も安藤も、茶の湯やアーキテクト派の住宅といったものが基本的には余裕の上に成り立っていることを見抜いていたからである。「安藤の出現以降のアーキテクト派住宅はすべて安藤の美学に引きずられていると言っても過言ではない。それは一方で唐物志向の成り金趣味を否定し、なおかつ返す刃で、『貧乏臭い』小住宅を否定し去っているからである」という洞察が導かれる。
ここでみた著者の思考のプロセスを要約するとこうなる。まずはアーキテクト派の「住宅とそこに住む人々を観察する(具体)。その上でアーキテクト派のニーズの本質をつかむ(抽象化)。抽象レベルでは同質の事象であるものとして、茶の湯における千利休へと論点がシフトする(具体化と文脈転換)。千利休の独創の本質を「反転」に求める(抽象化)。さらに安藤忠雄の建築を「反転」の視点から考察する(具体化と文脈転換)。こうして具体と抽象を往復し、次から次へと文脈を移動していくことによって、洞察が引き出される。アタマがいいとはこういうことだという見本のような展開だ。





