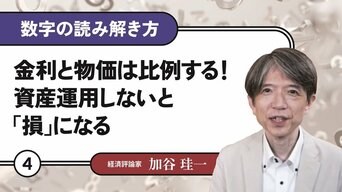※本稿は、菅野久美子『母を捨てる』(プレジデント社)の一部を再編集したものです。
母と一体になれた作文コンクールの受賞
ある日、私に大きな転機が訪れた。それは学校から届いた何かの作文コンクールの応募用紙だった。その用紙を目にした母に言われるがまま、小学生の私はそれに応募することになったのだ。
「お母さんの言うとおりに書きなさい。そのまま書けばいいからね」
記憶があやふやなのだが、はっきりと覚えているのは、眠い目をこすりながら夜中まで、母の言うままに400字詰め原稿用紙に鉛筆を走らせたことだ。
真っ暗闇の中、煌々と灯ったオレンジ色の電灯の光が、私の瞼に今も焼きついている。
眠くて記憶がなくなっていたが、朝起きると原稿用紙にはしっかりと文章ができていた。それは、母がほぼ書き上げたといっても過言ではなかった。
母は結婚する前までは国語教師で、特に作文指導が得意だった。
私はその作文コンクールで大賞を取り、全校児童の前で表彰された。家に帰ってそれを告げると、母は飛び上がって私を抱きしめた。断っておくが、その文章の8割近くは母が考えたものだ。だから今思うと、この行為は何とも後ろめたい思いでいっぱいである。
しかし実際のところ、当時の私には罪悪感なんて微塵もなかった。だって、あの母が喜んでいるのだから。それはイコール母が認められたことに等しかった。むしろ母がつくった文章であることが、母と私が一体になれた気がして、無性に嬉しかった。
そのとき、母は「これだ!」と思ったに違いない。世の中を見返すときがやってきたのだ。文才のある娘という、打ち上げ花火を使って――。
母のトクベツになれた日
それからというもの、私は母に言われるままに原稿用紙に鉛筆を走らせた。そんな事情など知る由もない担任の先生も喜んで、私に全国規模の作文コンクールの情報を頻繁に持ってくるようになった。最初、その文章のほとんどは母が書いていた。そのうち文章のテクニックがつかめてくると、しだいに私が書いた文章を母が添削するだけになった。
そして、私は次々に作文コンクールに応募しては、総なめにしていった。大賞や最優秀賞を頻繁に取ることはさすがに難しかったが、佳作や優秀賞には引っかかるようになったのだ。
作文コンクールで入賞するたびに母は狂喜した。そして、私をこう鼓舞するのだった。
久美ちゃん、もっともっと、たくさん賞を取るの。そうして、お母さんを喜ばせて。そして、耳元でとっておきの一言を囁いた。
「久美子は、お母さんの血を引いているのね――」
その言葉は何よりも私を歓喜させた。そして、気が付くと目からは大粒の涙がこぼれ落ちていた。私は、お母さんの血を引いている――。私は母の「トクベツ」なのだ。ずっとずっと母に自分を見てほしかった。その母が今、私を見ている! 私を見てくれている! 大事にしてくれている。私は、お母さんの身代わりになる。お母さんが生きられなかった人生を生きる。だから、お願い。私をもっと見て!
文章をうまく書けると、母に褒められる。そして母に褒められるためには、文章をもっともっとうまく書いて、いっぱい賞を取らなければならない。私はそう決意した。