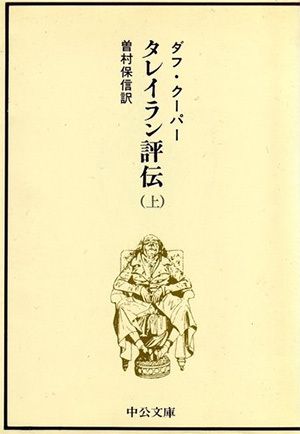『タレイラン評伝』と『ジョゼフ・フーシェ』という2冊の評伝に出合ったのは、30代になったばかりの頃だった。

東海旅客鉄道(JR東海)会長
葛西敬之
1940年、東京都生まれ。都立西高校から63年東京大学法学部卒業、日本国有鉄道入社。国鉄分割民営化に際し、「改革3人組」の1人に挙げられるなど、中心的な役割を果たす。87年JR東海発足に伴い、取締役総合企画本部長。90年副社長、95年社長、2004年より現職。
葛西敬之
1940年、東京都生まれ。都立西高校から63年東京大学法学部卒業、日本国有鉄道入社。国鉄分割民営化に際し、「改革3人組」の1人に挙げられるなど、中心的な役割を果たす。87年JR東海発足に伴い、取締役総合企画本部長。90年副社長、95年社長、2004年より現職。
20代後半でアメリカに留学した私は、地方の鉄道管理局に2年間勤めた後、国鉄の東京本社経営計画室の主任部員として戻ってきた。今後の国鉄全体の方向性はどのようにあるべきか――その命題を考える末端の作業部隊の指揮官として働きながら、一方でその時期の私はこれからも国鉄に勤め続けるかどうかを悩んでいた。そんなときに手に取ったこの2冊の評伝は、若い自分に大きな感銘を与えることになったのである。
18~19世紀のフランスを生きたタレイランとフーシェは、極めて共通点の多い人物だった。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント