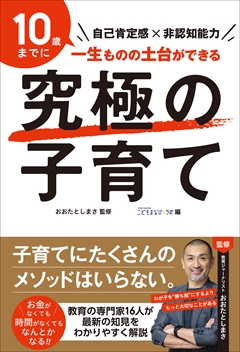さらに「凍りつき」というタイプもあります。これは、虐待やいじめ、それから支配的な家庭に育った子どもに多いタイプですね。
子どもは3歳くらいになると、「こういうことをやりたい」といった自我が出てきます。でも、自我を出したときに親に否定されると、子どもは「いい子でいないといけない」と思うようになります。ただ、自我に逆らって「いい子」でい続けるのは大変です。
小学校ではずっと「いい子」だった子どもが、中学生になるといきなり不登校になっちゃった――。「いい子」でいることに疲れてしまうと、こういうことが起きるのです。
第1段階は生後3カ月で決まる
そういった点も含めて、「キレやすい子ども」になってしまうかどうかは、親のかかわり方にかかっているといっていいでしょう。
じつは、安定した子どもになるかどうかのまず第1段階は、生まれてから3カ月くらいのあいだに決まってしまいます。
生まれたばかりの赤ちゃんは、まだはっきりとものを見ることができません。音は聞こえてにおいも感じられるけど、その正体はわからない。だから、とっても不安です。体も動かせませんから、赤ちゃんができることは泣くことだけ。
その泣き声を聞いた親が、しっかりと赤ちゃんの不安を察知して、おむつを替えてあげたりミルクをあげたりするなど、赤ちゃんが感じているいろいろな不快を快に変えることで、赤ちゃんは少しずつ安心して穏やかになっていくのです。
その3カ月のあいだに、たとえば未熟児で生まれたりなんらかの病気を持っていたりしたことで親から離される経験をした子どもの場合、分離不安(愛着を持つ人やものと離れることで、持続的に強い不安を感じること)を生じやすくなります。
だから、幼稚園や保育所に行く際にもすごく泣く傾向にある。その原因は、生まれてから3カ月のあいだの親子の接し方にあるのです。
親が怒鳴るときは子どもの脳も怒鳴っている
そのあとも、子どもがキレやすくなるかどうかは、親のかかわり方が大きく左右します。
3歳くらいになって感情が出そろってくると、子どもは親の感情や行動を真似していくようになります。
自分にとってマイナスになる場面では、嘘をつくとうまくいくことを見ていると同様の行動をする。また、親から怒鳴られている子どもは、人と接するときや人になにかをしてもらいたいときには怒鳴るようになる、という具合です。
だから、親から虐待された子どもは、学校ではいじめっ子になりやすくなるといいます。
このことには、脳内にある「ミラーニューロン」という神経細胞の働きが関連しています。これは、文字通り、「鏡の神経細胞」です。これによってどんなことが起こるのか。