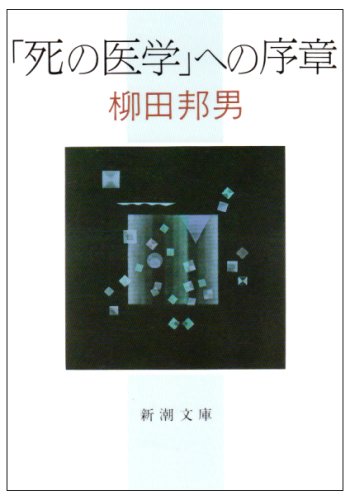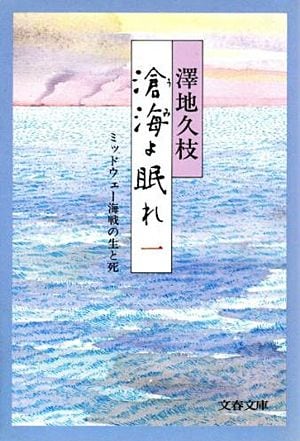「生と死」というテーマは、あらゆるノンフィクション分野に通ずるものです。なかでも人間の本質が見えてくる場面として、戦争の極限状態が挙げられます。そしてその極限状態は「戦場」にだけあるものではありません。
「銃後」と言われた兵士の妻たち、母親、家族、恋人などを通して戦争を描いてきた作家に澤地久枝さんがいます。彼女が「残された者」の視点でミッドウェー海戦の全体像を描いた『滄海(うみ)よ眠れ』は、日米双方の遺族への聞き取りと、何千人という戦死者への調査を行った大作です。この本の中に、戦死したある兵士の隠れた恋人が登場する、印象的な個所があります。戦後何十年も経ってその兵士の正妻が再婚するのですが、その際に彼女が「彼が私だけのものになった」と言うのです。男と女の関係がどうこうというよりも、そこには戦争が引きずる問題の深さが端的に語られていると思います。
また、現代の戦争の新局面を明らかにしたものでは、高木徹さんの『ドキュメント 戦争広告代理店』が重要です。戦争の「情報戦」といえば、多くの場合スパイ戦を意味します。しかし本書が明らかにしたのは、現代の戦争では片方の請け負いPR会社がスパイ以上の影響力を持つこと。現代の戦争は言葉通りの宣伝戦となっており、その虚実を理解するのが難しくなりつつある。本書はそこを理解するヒントを初めて発掘した国際性のある作品です。
辺見じゅんさんの『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』は、シベリアに強制収容された兵士たちが、飢えと寒さと強制労働の中でどう生き、どう死んでいったかを描きます。ある満鉄職員の遺書を日本に届けるために、その内容を仲間たち6人が分担して暗唱し、文字を書きつけた紙片を小さく丸めて、靴の底やズボンの裾に縫い込んだりして持ち帰る。たとえどんな限界状況や不条理な世界に置かれても、人間は家族愛や友情に支えられると、人間らしく生き抜くことができる――本書はそのシーンを実に感動的に描き出しています。
このように、戦争は多面にわたる問題を残します。戦争の記録を読むことは、いつの時代でも最重要、なにはともあれ読んでほしいと思います。
感動的という意味ではハンセン病の作家・北条民雄の評伝『火花』(髙山文彦著)も素晴らしい。強制収容所やハンセン病患者の隔離政策……。もはや人生に何かを期待することができない、という現実がそこにはある。しかし、人生や将来への期待が閉ざされたとき、残されるのは本当に絶望だけなのでしょうか?
本書を読むと、決してそうではないことがわかります。北条民雄は『いのちの初夜』で、人生が病気や差別や偏見の中で疎外されたとき、精神がどのような状態に追い込まれていくのかを克明に描きました。髙山さんは〈生命だけがびくびくと生きている〉(『いのちの初夜』)といった北条民雄の言葉を改めて今の時代に突きつけ、彼の生涯を感動的に見つめ直したのです。