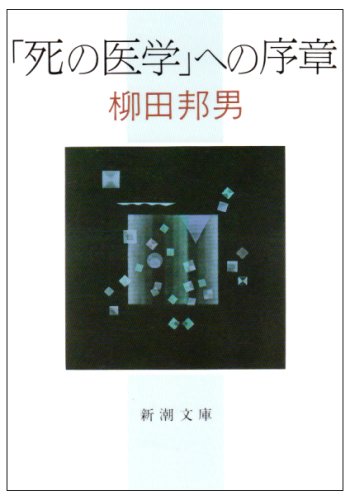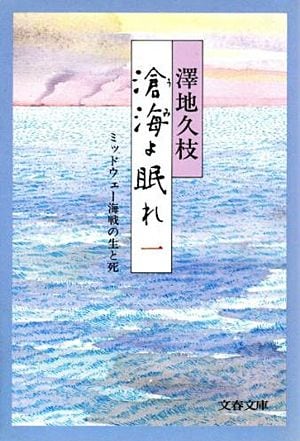「人生に大切なものは何か」読んで学び、気づく

日本のノンフィクション作品は、常に「時代」を映し出してきました。戦争をテーマとした作品が中心だった戦後の約20年間があり、1970年代には現代社会の抱える新しい病理=公害などの問題が描かれ始める。そして80年代から90年代にかけて、新たな特徴として現れたのが「闘病記」というジャンルです。
なぜ「闘病記」がノンフィクションの新しいジャンルとなったのか。
それは60年代以降、医学がめざましい発達を遂げる一方、医療者側が壊れた機械を修理するような感覚で人体を診るようになり、人間の精神性や、患者と家族との関係性などについての議論が忘れ去られてきたからでしょう。生と死の交錯する現場の不条理はまさに現代的なテーマであり、ジャーナリストや作家のみならず、医者、患者、病気に直面したあらゆる人々によって幅広く描かれるようになったのです。
その一冊に挙げたいのが、芥川賞作家・重兼芳子さんの遺作『たとえ病むとも』です。癌を宣告された後、重兼さんはホスピスのボランティアとなります。様々な形で旅立つ人を見つめる中で、彼女は徐々に「死」というものと親和していく。死を恐れなくなり、ある種の心の平安を得ていくのです。
彼女は死を前にしても、あるいは死を前にしたからこそ、精神性高く生きることを目指します。医学の発達は命を医療者任せにし、人間の「死」を覆い隠してしまうところがある。その中でいかに死と向き合い、自らの生き方を決定していくか。それを個々人が戦略的に考えなければならないことを、本書は浮き上がらせています。
81年、国立千葉病院の精神科医長だった西川喜作さんが、2年間の闘病の末に癌で亡くなりました。『「死の医学」への序章』は、西川さんから手紙をいただいて交流を始めた私が、伴走者のように彼の死を見つめた記録です。人の心を見る精神科医が死に直面し、自らの心理の変化を言葉にしていく――「死の医学」とはその中で西川さんがつくりだし、実践した言葉です。
自分自身がどのように死を迎えたいか。西川さんの闘病の記録は、現代が「自分の死をつくる時代」であることを、事実をもって示しました。そしてそれは、「闘病記」がノンフィクションの重要なジャンルとなった理由でもあるでしょう。