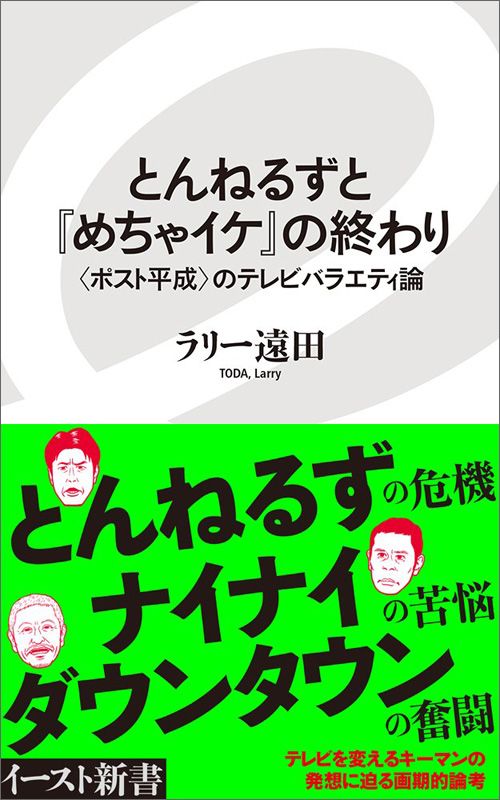しかし、ゴールデンに上がった『めちゃイケ』を初めて見たとき、『めちゃモテ』が好きだった私は、ちょっとした違和感を抱いた。番組のターゲットが変わり、予算も増えたことで、番組のテイストががらりと変わったように感じたのだ。番組のなかで出演者や演出サイドがチームとしての一体感をやたらと強調するようになったのも、『めちゃイケ』が始まってからではないかと思う。
ほとんどの期間で演出を務めた片岡飛鳥は、ドキュメンタリー的な手法を駆使して、岡村を含む出演者たちを精神的に極限まで追い込むことで、その素顔を引き出そうとした。だから、『めちゃイケ』では出演者が本気で怒ったり、泣いたりするような場面がたびたびあった。
『めちゃイケ』では、ひとつの企画が行われた後に、出演者がそれに向けていかに真面目に努力していたか、などということがナレーションで語られたりすることがある。率直にいって、個人的には『めちゃイケ』のそういうところが苦手だった。「実は裏でこんなにがんばっていたんです」などということをバラエティ番組の中で明かす必要があるのだろうか、と疑問に感じていたのだ。
根底の「なんでもさらけ出す青臭さ」
出演者が努力した結果、面白いものが生まれたのであれば、その「面白いもの」だけをそのまま見せてくれればいい。それが生まれるまでに努力した過程を見せてほしくはないし、見せるべきでもないのではないか。マジシャンが見事なマジックを披露したあとに、舞台上でそのタネ明かしを始めるなどということがあるだろうか。漫才師が面白い漫才を演じたあとに、ネタづくりの苦労について語るということがあるだろうか。
『めちゃイケ』でそういうものを見せられるたびに白々しい気持ちになり、私はいつしか『めちゃイケ』の熱心な視聴者ではなくなっていた。個々の企画で面白いと思うことはあっても、『めちゃイケ』の根底にある「なんでもさらけ出す青臭さ」みたいなものには最後までなじめなかった。