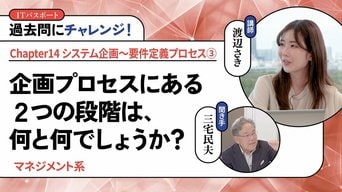曖昧な人事考課は単なる時間の無駄だ、と誰もが思っている。それでも多くの企業でこの方法は「必要悪」として存続してきた。もっと効率的で、中立的な仕組みをつくれないものだろうか。
実績主義の人事考課はほとんどの企業で当たり前のように行われている。それを廃止すれば、マネジャーも一般社員もこぞって安堵の吐息をもらすだろうと、あなたは思っておられるかもしれない。だが、その場合、モチベーションやパフォーマンスそのものに、どのような影響があるのだろう。
これは人事関係者の間でも経営幹部の間でもずいぶん前からひそかに議論されてきたことだ。企業は一方では、この仕組みを完全に廃止することに大いに魅力を感じている。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント