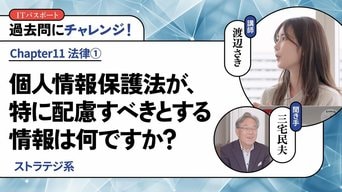専門家集団が解けなかった難解な問題を専門外の素人たちが解いてしまうサイトが米国にある。製品開発においても素人が強みを発揮するケースについて、企業の実例をひいて解説する。
「専門家は素人に負けない」の思いこみを捨てよ
メーカーが思いつく前に消費者が革新的な製品を作っている」。本連載で一貫して発信しているメッセージだが、今もってメーカーで首を傾げる方は多い。
メーカーは製品の専門家、消費者は素人。消費者は目の前に製品があれば改良案ぐらいは言えるかもしれないが、全くゼロの状態から画期的アイデアを思いつくほどの想像力は持っていない。専門家が素人に負けるはずがない。メーカーの反応にそうした自負が見てとれる。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント