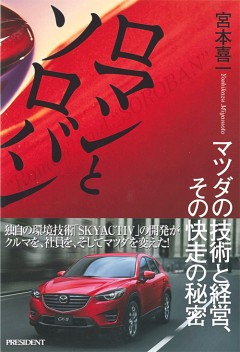「コスト削減活動は全員の手柄です」
――それがアテンザから始まる一連のいわゆるZoom-Zoomな製品ということですね。
そうです、2002年5月に発売したアテンザがZoom-Zoomの第1号です。このモデルの主査を務めたのが現在会長を務めている金井誠太です。この2002年以降、業績は回復軌道に乗りました。これには輸出に有利な円安という為替の環境に助けられた側面もあります、当時の生産体制の前提は国内中心でしたから。そんな状態のまま、リーマンショックが来たというわけです。
このリーマンショックに打ち勝つためには、付加価値を持った技術と製品の開発を心がけ、販売促進費に頼らなくてすむ、収益率の高いクルマを開発すべきだと、改めて認識しました。しかもこうしたクルマ造りをしながら、円高の環境下でも利益を確保しなければなりません。そこで必要になるのは、より高度なクルマを、従来のクルマよりも低いコストで造ること。現在のマツダの「モノ造り革新」「技術革新」の具体化はここから生まれました。
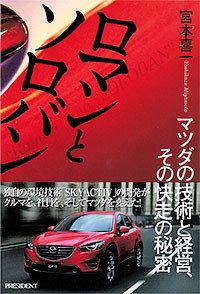
――モノもの造り、技術革新ということばは、マツダに限らず、どの企業でも掲げる方針ではありませんか。
マツダの社内には以前から「ONE MAZDA」という考え方があります。つまり、全体最適、会社として最もよい判断をするという当たり前のことです。ところが、この“会社として”という考えが、部門間の厚い壁に阻まれてなかなか前進しない時期が続いていました。そうこうしているうちにリーマンショック。このショックによって、自分たちのこうした現実がより明確に見えてきたのです。自分たちの部門だけがよければそれでよし、というわけではない、製品が売れてはじめて、そのお金をもとに自分たちの次の製品が開発できるという現実です。
――生産部門と開発部門のスタッフが同じ建物に同居しているのに、お互いに口も聞かないことがあった、という話もお聞きました。
そんなこともありましたねぇ。でも、今は違いますよ。リーマンショックを機に、社内の空気は一変しました。まず、2009年の春、役員全員が結集して徹底したコストダウンの検討に没頭しました。現行のモデルをビス一本にまで分解して、各役員の責任領域、たとえば生産技術、購買などの立場から、コストダウンのアイデアを出す作業です。これは毎週1回、終日、ひとつのモデルについて行ないます。それを半年間ほど続けました。
細かいものまで見直しました。たとえば、部品識別用のワッペン。「これ生産現場でほしいのか? 1枚10円もするぞ。現場は姿形で判別できないのか?」という指摘までしました。納入される部品に貼ってある傷つき防止シールも無駄なので廃止しました。そうした検討の過程で、とんでもないものも見つかりましたよ。部門の壁はこんなにも厚いのかと改めて感じました。
このコスト削減活動は、役員や特定の個人の手柄ではありません。全員の手柄です。これをきっかけに、各部門のエンジニア同士が「そろそろ会社が儲かることをしようや」と言ってくれるようになりました。