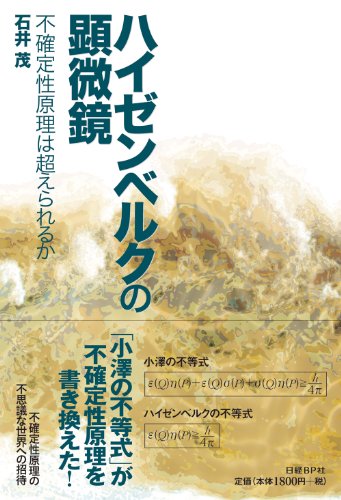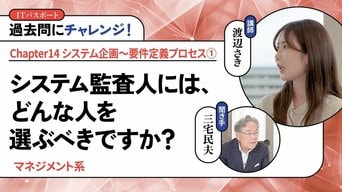かつて福澤諭吉は「日本人は西洋科学の精神を学ばなかった」と嘆いた。「自然哲学」という言葉からもわかるように、科学はもともと哲学から派生したものなのだ。
しかし、日本人は「何が自分たちにとって役立つか」という功利性の部分にだけ目を向け、科学のバックボーンともいうべき思想性を顧みることがほとんどなかった。その弊害は、昨今のエネルギー問題にも象徴され、何かアクシデントが起きると、「すべてやめてしまおう」という極端な反応を示すようになっている。
エネルギーを自然界からどう取り出して利用していくかを研究しているのが物理学である。その物理学の仕組み、そして物理学の限界を理解したうえで、エネルギー効率などのデータに基づきながら国のエネルギー政策を決めていくのが本筋だろう。

ここから先は有料会員限定です。
登録すると今すぐ全文と関連記事が読めます。
(最初の7日間無料・無料期間内はいつでも解約可)
プレジデントオンライン有料会員の4つの特典
- 広告最小化で快適な閲覧
- 雑誌『プレジデント』が最新号から読み放題
- ビジネスに役立つ学びの動画が見放題
- 会員限定オンラインイベント