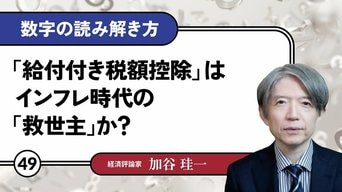第二次世界大戦中、捕虜となった日本人兵は収容所でアメリカ軍人たちとどのように過ごしたのか。小樽出身でハワイの日本人捕虜収容所長を務めたオーテス・ケーリさんの著書『真珠湾収容所の捕虜たち 情報将校の見た日本軍と敗戦日本』(角川新書)より、一部を紹介する――。
収容所でも靴を脱ぐ「日本人の習慣」を尊重する
ことわっておくが、アメリカの捕虜収容所といってもいろいろあり、時と所によって現実にはかなりの相異があったようだから、私のいた所の事情がすべてに通じるとは言い切れない。収容所を動かしている人間によって、捕虜生活の雰囲気が相当左右されることも事実である。日本語が出来、日本人をよく理解している人が多かったという点ではここは他に優っていたと今も思っている。
私が柵へ入ってゆくと、柵長が走って来て、日本の軍隊式に大げさな敬礼をするというようなことが、入所早々の柵では演じられた。みんなに一つのテントに集まってもらう。テントには床板があったが、もちろん靴のまま上がるようにこさえてあるものだ。
ところが日本の捕虜は、ほとんどが靴を脱いで上がり、いつも雑巾がけして光らせていた。家の中はこうしないと落ち着けないらしい。そのかわり靴をはくのは勢い突っかけになるので変形するのが早かった。
こういう“日本家屋”へ私の同僚の多くは靴のまま怪しむことなく入って行ったが、私は日本人の習慣を尊重した。といって、いちいち編上靴を脱いでもいられないので、床の端に腰をおろすのが常だった。
まず人間味から入ってゆく
私は日本の捕虜に接する根本的な態度をこういうふうに決めていた。
何よりもまず人間味から入ってゆく。彼らはアメリカ人から見れば、てんでまともな人間として扱われて来なかったのだ。日本とアメリカと、政治上の立場、戦争での敵対関係、習慣――相反することはいくらあろうと、人情はそれらを超えて滲透する。
私は元来は情報係将校だった。だから情報任務はやらなければならなかった。いやな仕事だと思うこともあった。しかし、戦争を早く終結さすために積極的に情報を取るべきだと考えていた。